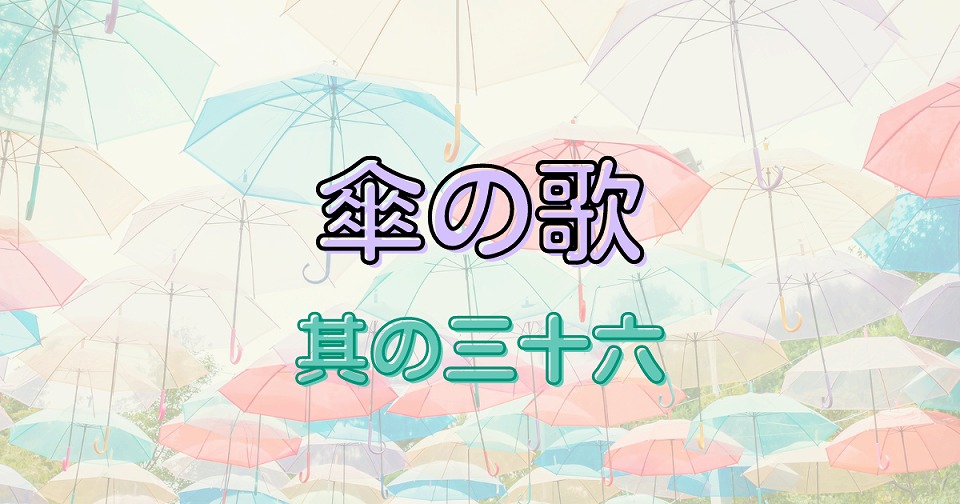ジュラ紀にも梅雨があったかもしれないこうもり傘の遠いい記憶
杉﨑恒夫『パン屋のパンセ』
杉﨑恒夫の第二歌集『パン屋のパンセ』(2010年)に収められた一首です。
実際に恐竜がいた時代を直接目にすることもなければ、その時代の実際の映像があるわけでもありませんが、図鑑や映画などを通して、恐竜がいた時代に思いを巡らすことは、とても楽しいものです。
さて、掲出歌は、恐竜がいたジュラ紀を想像しています。いま主体の手元にある「こうもり傘」から、時間的に遠い昔のジュラ紀の「梅雨」を想像しているのです。
この飛躍が楽しい一首ですが、「こうもり傘の遠いい記憶」の「遠いい」が効いているのではないかと思います。
「遠い」でもいいわけですが、「遠いい」となっています。このように詠われると、「遠い」よりも「遠いい」の方が、やわらかに感じますし、またより遠い昔であることのようにも思われます。「遠いい」には、主体が本当に遠い昔に感じている雰囲気もありますし、やさしい視線も感じます。
「ジュラ紀」と聞いたとき、恐竜のことはすぐ想像しても、そのときの天候の季節的な変化をあまり想像することはないでしょう。
「ジュラ紀にも梅雨があったかもしれない」と詠われることで、実際に梅雨があったかなかったかに関わらず、読み手はジュラ紀の梅雨を想像してしまいます。ジュラ紀の恐竜は、梅雨に濡れたこともあったのでしょうか。樹々の下に隠れて、雨を凌いだこともあったのでしょうか。さまざまな想像があっという間に広がっていくのではないでしょうか。
この「こうもり傘」は、ひょっとするとジュラ紀に空を飛んでいた恐竜の末裔のようなものなのかもしれません。主体がジュラ紀の梅雨を想像しているのですが、それはこうもり傘の記憶そのものでもあるのです。こうもり傘に残っている記憶を、主体が読みとっているともいえるでしょう。
こうもり傘という日常のアイテムから、ジュラ紀へと思いを誘ってくれる、スケールの大きな一首ではないでしょうか。