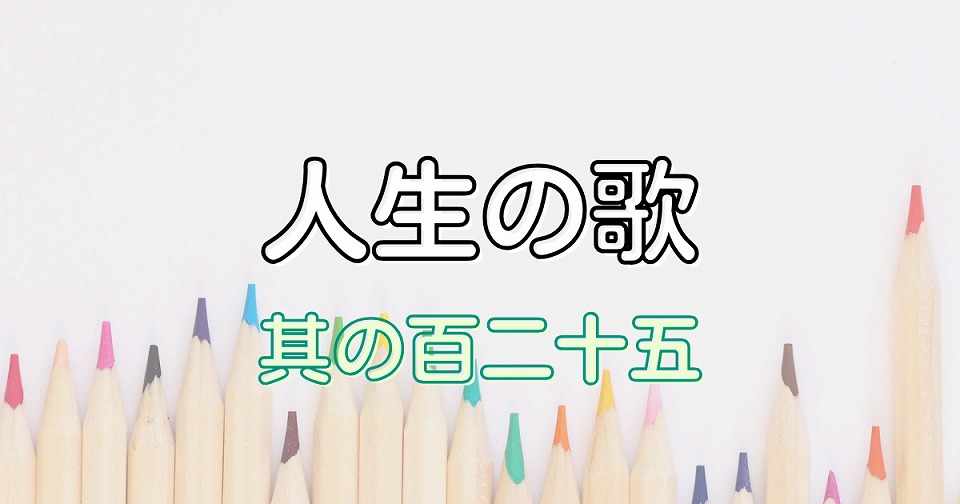うしなへば自由になれる きつかけは些細で後はとつぴんしやん、と
西橋美保『うはの空』
西橋美保の第二歌集『うはの空』(2016年)に収められた一首です。
「うしなへば自由になれる」と詠い始めらますが、失うものが一体何であるのかは、この一首には具体的に書かれていません。
方向性としては二つ考えられます。
一つは、嫌なこと、断ち切りたいこと、煩わしいことといったマイナス面のものを失うということです。確かに、そういったマイナス面をなくすことができれば、自分を縛りつけていたものから「自由」になれるのではないでしょうか。
もう一つの方向性は、夢や希望、可能性といった、一般的にはプラスと見られているものを失うということです。プラス面を失うということは”喪失”のような意味合いが強くなり、一見「自由」とはかけ離れていると感じるかもしれません。
しかし、夢や希望に固執していた状況があったとすればどうでしょうか。すんなりと自分が望む通りになればいいのですが、中々うまくいかず、夢や希望があることで逆に自分が追い込まれていたとすればどうでしょう。そのような夢や希望であれば、失ってしまった方が、「自由」に近づくのではないでしょうか。
マイナス面のものにしても、プラス面のものにしても、それとの関わりをもっている状態はある意味”不自由”な状態なのでしょう。関わりをなくすことで、「自由」になれるというのは、何となくわかるように感じます。
さて下句では、「自由」になるきっかけが詠まれていますが、「きっかけは些細」であると示されています。そして「後はとつぴんしやん、と」と続いていきます。
「とつぴんしやん」は、童謡”ずいずいずっころばし”に歌詞にも登場する言葉ですが、戸をピシャンと閉める様を表した言葉、また東北地方の昔話で語りおわった時に「おしまい」という意味の決まり文句として使われる言葉です。
失うきっかけは些細であるのに対して、最後は「とつぴんしやん」といった急で力強さが伝わる表現で、その落差にこの歌の味わいがあるように思います。
失うことは、一旦何かとの関係性をもち、その関係性をなくすことであり、その一連の流れこそが「自由」へつながるために必要なことなのかもしれない、そのようなことを感じさせてくれる一首です。