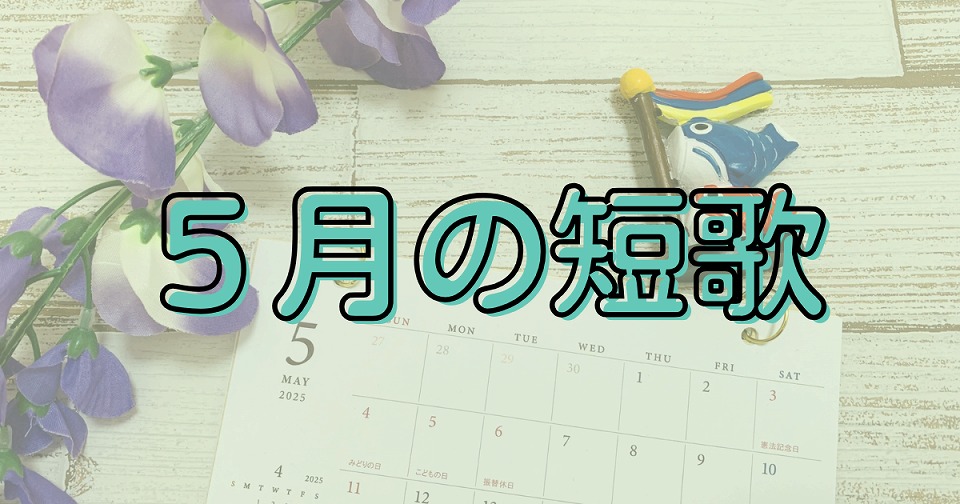「5月」に関わる短歌をピックアップしてみました。5月に詠まれたと思われる歌もあれば、別の月に詠まれている歌もあります。
5月の短歌
一枚の葉にも表と裏のあることを五月の風は教える
| 作者 | 松村正直 |
| 歌集 | 『駅へ』 |
 tankalife
tankalife五月のさわやかな風に、一枚の葉が吹かれています。最初、落ちた葉が路上を転がっていく様子をを想像しましたが、五月という季節であり、何度も読むと風に吹かれながらも枝にしっかりとついている葉がふさわしいように感じました。葉は表面を見せたり、裏面を見せたりする一枚の葉の動きをじっと見ているのではないでしょうか。たった一枚の葉でさえも、表と裏があることを伝えてくれるのです。風がなければ、表を裏を殊更意識することはなかったかもしれません。五月の風が吹くことによって、表と裏がはっきりと提示されたのです。表と裏があることは当たり前のことのように思いますが、普段我々がものを見る際、いかに一面しか見ていないかを改めて教えてくれるように感じます。たった一枚の葉から教えられることは、真理に近いものなのかもしれません。
パンプスもスーツも処分する五月わが総身に新緑は満つ
| 作者 | 松村由利子 |
| 歌集 | 『大女伝説』 |



五月といえば新緑の季節です。パンプスもスーツも処分したということは、もうそれらを使う必要がなくなったということでしょうか。断捨離という言葉が広まりましたが、この歌の場合何もかもを処分するというよりは、パンプスとスーツが具体的に提示されており、一般にいう断捨離とは少し異なるように思います。おそらく仕事で使用していたパンプスとスーツを捨てることによって、今後はもうそれらを身につけることはなくなるのでしょう。今まで身につけていたものをつけなくてもいい体は、気分的にも物理的にも軽々としたものに感じられるのではないでしょうか。「わが総身に新緑は満つ」という表現が、新緑の若々しさ、清々しさを想起させ、これまでの生活とは線を引き、新たな自分自身がスタートする、そんな前向きで新鮮なイメージを感じさせてくれる一首です。
いるんだろうけど家に入って来ないから五月は終わり蚊を見ていない
| 作者 | 永井祐 |
| 歌集 | 『日本の中でたのしく暮らす』 |



「いるんだろうけど」は蚊、「家に入って来ない」も蚊、そして「見ていない」も蚊です。「五月の終わりに蚊を見ていない」ことを詠った歌ですが、主体が見ていないはずの蚊の存在が、この歌においては前面に出てくるように感じます。家の中が軸となっており、そこが主体にとっての領域として提示されているように思いますが、その領域の外側はあくまで想像の域であり、認識のエリアの範囲外ということになるのでしょう。したがって、蚊の存在を想像はしても、蚊を認識したということにはならないのです。家の中に入ってきて初めて蚊を認識することになるのでしょうが、この五月は蚊が入ってこなかった、つまり蚊を認識することはなかったということだと思います。蚊を直接見ることはなかったにもかかわらず、読み手の中で蚊の存在が形成されていくような不思議な一首です。
五月雨にワイシャツ透けて青白い痩軀のきみよ禽の眼をして
| 作者 | 楠誓英 |
| 歌集 | 『禽眼圖』 |



歌集において、この歌を含む一連は、21歳という若さで自死した歌人・岸上大作について詠ったものです。この歌は岸上大作の代表歌でもある〈血と雨にワイシャツ濡れている無援ひとりへの愛うつくしくする〉を踏まえて詠われているでしょう。したがって「青白い痩軀のきみ」とは岸上大作自身を指すのだと思います。作者は、直接見ることはなかった岸上を歌の中でありありと立体化しています。「禽」とは鳥のことですが、痩軀でありながらも眼光だけは鋭かったであろう瞬間の岸上を「禽の眼」として捉えています。そこには敗れながらも、ある信念だけは絶やさないひとりの人物が浮かび上がってくるように感じます。五月雨のじめっとした感じが、ワイシャツと皮膚の触感を、そして雨に濡れる眼の表面のつややかさをより一層伝えてくる一首ではないでしょうか。
たいっかん、電気ついとる だけ言ってきみがみている五月の夜空
| 作者 | 岡野大嗣 |
| 歌集 | 『音楽』 |



五月の夜のことです。「たいっかん」とは体育館のことでしょう。学校かあるいは市民体育館などの近くにいるときの出来事でしょうか。「きみ」が「たいっかん、電気ついとる」とだけいって、夜空を見ている場面です。体育館ではなく「たいっかん」というところが非常にいいと感じます。二人の関係性がそこには表れているでしょう。体育館と正しくいわないで済む関係性、「たいっかん」といっても通じて受け入れられる関係性が出ています。電気がついていたからどうということもないのでしょう。ただありのままを「きみ」はつぶやいただけかもしれません。でも、そのありのままのつぶやきが、このときの二人にとってはこのときにしか共有できない瞬間であり、仮にまったく同じ発言が将来あったとしても、このときと同じ瞬間は二度と味わえないでしょう。そのような瞬間の手触りのようなものが「たいっかん、電気ついとる」に感じられる一首です。
ミカヅキモきもいきもいと顕微鏡かわりばんこに覗いた五月
| 作者 | 山田航 |
| 歌集 | 『寂しさでしか殺せない最強のうさぎ』 |



学校での理科の時間でしょうか。顕微鏡を使って色々な微生物を観察した時間を思い出します。「ミカヅキモ」は三日月の形状をした緑色の藻です。顕微鏡で見ると、細胞内の構造がくっきりと見えるため、じっと見ていると「きもい」という感じもよくわかります。「かわりばんこ」に覗いていたので、自分と相手がペアになって交代でミカヅキモを見ていたのでしょう。「きもいきもい」というのは本当にミカヅキモが気持ち悪かったというのもあるのでしょうが、それ以上にペアの相手に対するアクションのように感じられます。「きもいきもい」と騒ぐことで、相手がどれどれといって顕微鏡を覗く。相手も「きもいきもい」といってまた自分が顕微鏡を覗く。その一連のやりとりこそが楽しい時間をつくり出していたのではないでしょうか。「きもいきもい」と騒ぐことがそのやりとりをより盛り上げるための言動として効果的に機能していたのではないかと思われます。五月の心地よい明るさの中に、心地よい二人の出来事が表れている一首だと感じます。
五月はおもふ自分が窓でありし日の風通らせてゐしここちよさ
| 作者 | 渡辺松男 |
| 歌集 | 『雨る』 |



「自分が窓でありし日」とありますが、自分が窓であったという独自の発想が本当に楽しい歌です。初夏の風が心地よく通り抜けていく様子を想像しますが、それは人間としての自分のままに風を受けていると思うのではなく、窓であった日の自分が受けていた風を思っているのです。窓として風を通らせていたときの心地よさは、人間として受ける風の心地よさの何倍も心地よいのかもしれません。それは窓という存在のひとつの役割として、風を通すというものがあるからではないでしょうか。しかも暑い風でも寒い風でもなく、五月の風なのです。窓であったということに思いを馳せるだけで、五月の風の心地よさを存分に感じることができる一首ではないでしょうか。
葬列の傘を持つひと持たぬひと五月雨に足は等しく濡れて
| 作者 | toron* |
| 歌集 | 『イマジナシオン』 |



葬式の場面です。五月雨が降っていますが、傘を差さずに済むほど弱い雨ではないのでしょう。外に立つ参列者は自分で自分に傘を差している人もいるでしょうし、親族らのために誰か別の人が傘を差してあげているというケースもあるでしょう。差す、差さないではなく「持つひと持たぬひと」という表現からは、後者の印象を強く受けます。傘を差してはいるのですが、傘をもっている人ももっていない人も、足元までは傘でカバーすることができず、どちらも濡れてしまっているのです。「等しく濡れて」には、傘の有無にかかわらず、雨に濡れるという点における共有のようなものが感じられます。参列者の一体感といえばいい過ぎかもしれませんが、五月雨に濡れるという事象によって、参列者の心の境界が溶け出しているような印象が感じられます。足が雨に濡れるという何気ない点に注目した歌ですが、葬列という状況がその場の共有感を引き出していく、そんな一首ではないでしょうか。
ああ五月しずけき森はみどりして豊かなるもの多く語らず
| 作者 | 岡部桂一郎 |
| 歌集 | 『坂』 |



五月の森の静寂が伝わってきます。森は若葉を増やし、青々と広がっているのでしょう。活力に満ちながらも、決して騒がしいわけではありません。それは静かに静かに豊かさを満たしていくのです。「豊かなるもの多く語らず」から、まさに森の豊かさが感じられますが、豊かであるからこそ自ら誇張することもないのでしょう。人間でもそうですが、自分はあれもこれも所有していて豊かなんですと殊更周りにいいふらすような人は本当に豊かなのでしょうか。そのような人は物質的に色々もっていても、心の奥底から豊かとはいえないのかもしれません。この森は多くを語りません。語らないからこそ、この森に触れた人は、森の豊かさを実感できるのではないでしょうか。「みどり」あふれる森が眼前に広がって感じられる一首です。
パイナップル食べ終えた後のまぶしさよまあるい皿に五月のひかり
| 作者 | 小島なお |
| 歌集 | 『乱反射』 |



パイナップルは黄色が鮮やかな果物ですが、やはり太陽の光を浴びて育った果物というイメージがあります。つまり、パイナップルを食べるということは太陽の恵みを食べるような感覚があり、単に果物を食べているというだけに留まらない印象がないでしょうか。さて、パイナップルを食べ終えた後に、主体は「まぶしさ」を感じました。パイナップル自体がまぶしい感じがしますが、食べ終えた後に一層まぶしさを感じたということでしょう。皿にはもう食べるべきパイナップルはありません。しかしそこには「五月のひかり」が残されていたのです。窓から差し込んだ光かもしれませんし、パイナップル自体が皿に残した光かもしれません。とにかくパイナップルを食べる前には存在しなかった光が、パイナップルを食べ終えることで生まれたのだと思います。パイナップルの黄色と「五月のひかり」が相互に関係しあい、まさに明るさに満ちた瞬間を照らし出してくれる一首なのではないかと感じます。
死ぬ日まで祖父が植えいしトマトの芽早や伸び出でて五月終わりゆく
| 作者 | 永田淳 |
| 歌集 | 『1/125秒』 |



歌集において、この歌を含む一連は〈逢坂山に椎咲きにけり五月五日は祖父の命日となる〉という歌から始まります。祖父は五月五日までトマトの種を植えていたのでしょう。そして五月が終わろうとする下旬に、祖父の蒔いたトマトはもう芽を出して成長しています。祖父の命は五月にストップしてしまいましたが、祖父の心は止まってはいませんし、これからも主体の中に生き続けていくのではないでしょうか。祖父が植えたトマトの成長という目に見える事象から、目には見えないけれど、祖父と主体のつながりが感じられ、印象深い一首です。
やっと五月。読みさしだったさみどりの歌集を持ってベランダに出る
| 作者 | 虫武一俊 |
| 歌集 | 『羽虫群』 |



さみどり色の表紙の歌集でしょうか。その歌集を読み進めていたのですが、読みさしのままだったのです。読みさしだったのは、時間がなくて読了していなかったのかもしれませんが、楽しみな歌集だったので読んでしまうのがもったいなくて、あえて読み切ってしまわないようにしていたのかもしれません。とにかく続きを読むためにベランダに出たのでしょう。五月の心地よい雰囲気が伝わってきます。「やっと五月。」という初句の表現に、五月を待ち遠しく思っていた心境がよく表れていると感じます。この五月を待って、ベランダに出て歌集を読むという行為を行いたかったのではないでしょうか。「さみどり」と「五月」がさわやかに呼応し、心地よさを感じる一首です。
ふくよかに五月を纏うそら豆はレンズに映ることを選んだ
| 作者 | 笹本碧 |
| 歌集 | 『ここはたしかに 完全版』 |



そら豆の充実した実を「ふくよかに五月を纏う」と表現したところが魅力的です。五月そのものをふっくらと柔らかに、そら豆はまさに纏っている様子が浮かんできます。さて、この「レンズ」とはカメラのレンズのことでしょうか。主体がそら豆をカメラのレンズから覗いている場面かもしれません。そら豆をレンズに映すのでもなく、そら豆を撮るのでもなく、「そら豆はレンズに映ることを選んだ」なのです。主役はあくまでもそら豆であり、五月を纏うそら豆の美しさや充実ぶりは、レンズに映ることがすでに決まっていたかのよう印象じをもたらしてくれます。そら豆の鮮やかさが一首の最前面に提示されている歌だと感じます。
あ、と思へば相撲部屋にも感染者出てあやふきは五月場所なり
| 作者 | 池田はるみ |
| 歌集 | 『亀さんゐない』 |



「相撲とコロナ」と題された一連にある一首で、2020年の五月場所の中止が決まるまでを詠った歌です。新型コロナウイルスが流行した当時、さまざまなイベントやスポーツ大会などが中止に追い込まれました。大相撲も例外ではなく、感染者が出たことにより、五月場所は中止となりました。特に体と体をぶつけ合う大相撲は感染リスクは高かったと思われます。「あ、と思へば」にあっという間に感染が拡大していく様子が伝わってきます。歌集において、この歌の次の一首は〈五月場所とりやめとなりまつくろな五月の陽を見るわたしのこころ〉とあり、相撲好きの作者にとってはとても残念な思いが感じられます。
薄暗い部屋でもういいよの声を待ってた 春は五月になった
| 作者 | 岡本真帆 |
| 歌集 | 『水上バス浅草行き』 |



「もういいよ」と聞いて思い出すのはかくれんぼです。実際にかくれんぼをしていたわけではないのでしょうが、主体は誰かに対して、あるいは何かに対して、もういいかいと問いかけていたのではないでしょうか。ひょっとすると自分自身に対して問いかけていたのかもしれません。「もういいよの声」は、承認や許しを意味しているようにも感じられます。しかし、声は一体いつになったら訪れるのでしょうか。「春は五月になった」は、月が四月から五月になったと採れますが、表現としては「四月が五月になった」と詠われているわけではありません。通常五月といえば春ではなく初夏という方が適しているでしょうが、「春は五月になった」と詠われているのは、五月になっても春をまだ引きずっているということでしょう。もういいよの声を待つ春はまだ終わりません。六月以降になっても終わらないかもしれません。「もういいよ」の声だけが春を終わりにしてくれるはずですが、その声が訪れるのはまだ先になる、そんな予感を感じさせる一首です。
そのひとは五月生まれで「了解」を「りょ」と略したメールをくれる
| 作者 | 土岐友浩 |
| 歌集 | 『Bootleg』 |



言葉を略したメールをやりとりするくらいですから、かなり親密な関係なのかもしれません。少なくともビジネス相手というわけではなさそうです。五月生まれと「りょ」と略す人であることは直接何かが関係しているわけではないのでしょうが、このように詠われると因果関係があるように感じてしまいます。「りょ」とだけメールする潔さのようなものが、初夏のさわやかなイメージをもつ五月生まれとどことなく通じるのかもしません。さて、四句は六音で字足らずとなっていますが、読むときは「りょ」の後に一音分の空白を添えて読むため、四句は実質七音で構成されているといってもいいでしょう。「りょ」と略すことと、四句の字足らずが呼応しているところも面白く感じる一首です。
縫い目なき五月の風を浴びていた肩幅のままあなたは眠る
| 作者 | 大森静佳 |
| 歌集 | 『ヘクタール』 |



「縫い目なき五月の風」からは、何の遮断もない、何の抵抗もない、まっさらな風を想像します。その風はあなたに向かって吹き、あなたはその風を今もこれまでもずっと浴びてきたのでしょう。その風によってクロースアップされるのは、顔でも手でも全身でもなく「肩幅」なのです。もちろん風は体のあらゆる部位に吹いていたのでしょうが、肩幅という部分が強調されることで、肩幅も風もそれ自身の存在を際立たせているような印象を受けます。風を受けた肩幅、そのままにあなたは眠ると詠われ、ここであなたの存在が顕ちあがってきます。「眠る」のは一日の眠りでしょうか、それとも永遠の眠り、つまり死を指すのでしょうか。この肩幅には、縫い目のない風を浴びた清々しさとともに、容易には触れ得ぬ何かが同居している、そのように感じられる一首です。
わが横に五月のひかり座りゐて明日といふは触れ得ざるもの
| 作者 | 横山未来子 |
| 歌集 | 『花の線画』 |



縁側でしょうか、あるいは公園でしょうか。「五月のひかり」が主体の傍を照らしています。真夏の陽射しのように暑いわけではなく、とても心地よい光なのだと感じます。「わが横に」「座りゐて」という表現が、「五月のひかり」の存在を立体化しています。このような心地よい日常の一場面なのですが、下句が印象的で「明日といふは触れ得ざるもの」と展開していきます。時間軸で見れば、確かに明日というのはまだ訪れていない時間であり、今現在は明日の中に生きているわけではありません。触れ得ないというのは、言葉の上では理解できます。しかし、このとき主体は言葉として理解したのではなく、「五月のひかり」の存在によってそのことを感じたのでしょう。光の体温が「触れ得ざるもの」の体感をさせてくれたところに惹かれる一首です。
風車からから回れ父親が我にはぐれし五月の砂場
| 作者 | 安藤美保 |
| 歌集 | 『水の粒子』 |



父親と一緒に砂場で遊んでいた子どもの頃を思い出している場面でしょうか。最初は一緒に砂場にきたのですが、いつの間にか父親の姿が見えななったのだと思います。父親がどこかに去ったという表現ではなく、「父親が我にはぐれし」と表現されているところがポイントでしょう。主体が父親からはぐれたのではなく、父親の方が主体からはぐれてしまったという逆転の構造が、若干の違和感を五月の砂場につくりあげています。父親がはぐれた砂場には、風車がからからと回っていたのでしょう。もっともっと「からから」と音を立てて回れと主体は感じたのかもしれませんが、「からから」にはかすかに淋しさが宿っているような印象を受けることは否定できません。
五月野は草も和し風立てばかぜのすがたに靡きわたれり
| 作者 | 沢田英史 |
| 歌集 | 『異客』 |



「五月野」(さつきの)とは五月の野原を表す夏の季語です。五月野一面に生い茂る草は「和し」、つまり柔らかいイメージとして感じられたのでしょう。「草も」の「も」とあるので、元々「五月」という季節自体が穏やかで柔らかない印象がある中で、その一部を形成する草も柔らかだといった感じでしょうか。さて、五月野に風が吹けば草が靡くのですが、それは「かぜのすがた」に靡くと詠われています。草が「和し」であるところから、風に吹かれた草が「かぜ」そのものと同化するようなイメージへと展開しています。五月ならではの草の姿が立ち上がってくる一首です。
アマリリスあうれりうすとつぶやいて女子校通りの五月をよぎる
| 作者 | 岸原さや |
| 歌集 | 『声、あるいは音のような』 |



季節は五月。女子校通りを歩いているところでしょうか、それとも自転車でしょうか、あるいはバスや車ででしょうか。女子校通りをよぎったのですが、「五月をよぎる」という表現が、単に通りをよぎるというに留まらず、五月という季節そのものを感じて、その五月の中を移動しているような印象をもたらしてくれるのではないでしょうか。楽しいのは初句二句の「アマリリスあうれりうす」の言葉の並びです。「あうれりうす」は古代ローマ皇帝の名前を想像させます。「アマリリス」と「あうれりうす」の歴史的あるは物質的な関係性は直接ないように思いますが、音韻の上では非常に密接に関係しているでしょう。主体はこのときアマリリスを見たのかもしれません。そのときふと「あうれりうす」という言葉が口をついて出てきた、そんな場面でしょうか。リズム感もよく、勉学という意味では「あうれりうす」と「女子校」が若干関連しているように感じます。「アマリリス」から「あうれりうす」への展開が、読んでいて心地よい一首です。
口中に、否脳中深く刻まれてひねもすわれは五月の茗荷
| 作者 | 内藤明 |
| 歌集 | 『薄明の窓』 |



「五月の茗荷」というと、旬よりは少し前の茗荷かと思います。「口中に」は茗荷を口に含んだ様子と関連する表現ですが、すぐその後に「否脳中に」と展開していきます。深く刻まれるのは何でしょうか。茗荷を食べると物忘れをするなどといわれますが、「脳中」と「茗荷」とが関係し、記憶のようなものが深く刻まれるのかもしれません。「ひねもす」とは一日中のこと。最初は茗荷を食べるという行為からスタートしているのでしょうが、やがて主体自身が茗荷そのものとなって一日中を過ごしているようなイメージでしょうか。そこに人間と茗荷との境界は薄れていき、記憶も物忘れも何もかもが溶け出して、残るのは「五月の茗荷」だけなのかもしれないと、そのようなことを感じてしまう一首です。
昨夜のゆめの輪郭強きあたりより叩くふとんに五月の風位
| 作者 | なみの亜子 |
| 歌集 | 『鳴』 |



昨夜、主体は夢を見たのでしょう。朝目が覚めても、その夢がおぼろげながら記憶に残っている状態です。はっきりとは思い出せない部分もありながら、夢の輪郭だけは思いのほかはっきりと感じられているのだと思います。「輪郭強きあたりより叩く」とあるので、夢の輪郭は、ふとんの特定の場所に関連づけられているようです。夢なので、頭や記憶、想像と関連づけて、例えば枕を置く位置を指しているのかもしれませんし、夢の内容からそうではない別の場所が夢の輪郭と関わっているのかもしれません。とにかく、昨夜の夢と関連した場所から、ふとんを叩いているのです。ふとんを叩くのは夢の記憶を追い払おうとしている行為なのでしょうか。それともおぼろげな記憶を再度取り戻そうとしている行為なのでしょうか。夢の輪郭を感じながら叩くふとんに、五月は風向きを示しています。その向かう先はどちらでしょうか。夢と風位が淡く結びつくように感じられる一首です。
緑金の包囲せまりくる五月あしたは魂の低く脈うつ
| 作者 | 高倉レイ |
| 歌集 | 『薔薇を焚く』 |



「緑金の包囲せまりくる」とは、樹々や若葉が生い茂る五月の自然の様子を意味している表現でしょうか。「包囲」といわれると、どことなく窮屈な感じがし、また「せまりくる」からは、追い立てられているような印象を受けます。そこには新緑を心地よいと感じている気持ちはほとんどなさそうに思います。「あした」とは朝のことでしょう。攻め立てられるように感じられる五月の朝は、「魂の低く脈うつ」朝なのです。朝、血圧が低いというのはよく聞きますが、魂が低く脈うつというのは初めて聞きました。体の問題ではなく、心の問題として、低空飛行の主体の姿を想像します。新緑は見方によっては清々しさをもたらしますが、主体の朝の捉え方からすれば窮屈さを感じるものであり、そこに何ともいえない暗さを感じてしまう一首です。
五月晴たんぽぽの絮一列にくすんとくさめ風邪のわたくし
| 作者 | 石川不二子 |
| 歌集 | 『ゆきあひの空』 |



五月晴は、梅雨の合間の晴れを意味する場合と、五月のさわやかに晴れわたった空を意味する場合があります。歌集において、一首後に〈大風邪ののちの鼻風邪空澄みて沖縄は梅雨に入りたりといふ〉という歌があるため、ここでは梅雨前の晴れた様子を指しているのでしょう。さて、たんぽぽの咲きならぶ景を見ている場面でしょうが、主体は風邪をひいており、くさめ、つまりくしゃみが出てしまったのです。主体は風邪でつらいのかもしれませんが、晴れた空、たんぽぽ、そして「くすんとくさめ」というリズミカルな表現から、どこか軽やかさのようなものも感じます。客観的に自分を見ているような余裕が感じられる一首です。
ぶよぶよの赤子の口に風かよふ五月いはれなき生のはじまる
| 作者 | 小池光 |
| 歌集 | 『廃駅』 |



五月に生まれた赤子を見つめている場面です。赤子を「ぶよぶよ」と表現していますが、ここには好悪は感じられず、ただ見たままをストレートに表現したのだと思います。五月の風が赤子の口を吹いていった。そのとき主体は「いはれなき生」が始まったと捉えているのです。確かに、なぜ生まれてきたのかを赤子に問うても、理由や根拠が述べられることはないでしょう。いわれがないことは、すなわち生とは不思議なものであり、とても尊いものであるという思いを意味してもいるのではないでしょうか。赤子の誕生を手放しで喜んでいるわけではなさそうですが、決して否定的に捉えているわけではありません。誕生は自らの思考の及ばない、手の触れられない領域であると認識しているのだと思います。「いはれなき生のはじまる」ことは幸か不幸かわかりませんが、少なくとも生が簡単に説明のつくものではない神秘的なものであることだけは確かに感じられる一首です。
産めやしない、産めはしないがアメジスト輝け五月なる疾風に
| 作者 | 黒瀬珂瀾 |
| 歌集 | 『ひかりの針がうたふ』 |



「産めやしない」は、自身が男性であり、子どもを産むことができないことを改めて自分に確かめているのでしょう。その後「産めはしない」と続き、産むことができないことに対する負の思いが強いのかもしれません。しかし「産めはしない」の後は「が」と展開していきます。五月の疾風にアメジストが輝くことを希求する姿は、出産できない自分を一部受け入れたことによって現れた姿なのではないでしょうか。アメジストの凜として立つ紫は、少々の抵抗では揺るがない存在感を放っています。出産できないことに対する負の感情が少し和らいだとき、自分自身を受け入れることができた象徴として、五月の疾風に輝くアメジストがいつまでも印象に残り続ける一首です。
喉から胸のあたりに甘やかな痛み兆して五月は終る
| 作者 | 近藤かすみ |
| 歌集 | 『雲ケ畑まで』 |



「痛み」とありますが、風邪を引いているわけでもないでしょうし、胸の病気を患っているわけでもないでしょう。なぜなら「甘やかな痛み」だからです。では、甘やかな痛みとは一体何でしょうか。過去に起こった出来事を思い出すときに、喉から胸のあたりが締めつけられるように感じることがありますが、そのようなものを指しているのかもしれません。それは思い出したくないことかもしれませんし、思い出として貴重なものだけどもう二度とそのときの時間は訪れないことへの何ともいえない気持ちのようなものかもしれません。過去の振り返りは年中いつでも起こることですが、ここでは五月という季節に限定していることによって、主体独特の体験として立ち上がってくるように感じる一首です。
「いつかこの丘の上に家建てたいね」カレンダー5月のイラストの丘
| 作者 | 九螺ささら |
| 歌集 | 『ゆめのほとり鳥』 |



カレンダーの5月に丘のイラストが描かれているのでしょう。その丘は素敵な丘に見えたのでしょうか。「いつかこの丘の上に家建てたいね」という発言を引き出すほどに、魅力的な丘なのではないかと思います。写真ではなく「イラストの丘」ですから、実在はしない丘かもしれません。丘が実在しなければ、その丘の上に家を建てることも実現することはありません。「いつか」から窺える通り、本気で計画しているというよりも、イラストの丘に家を建てられたらいいよねという希望を、今相手と共有していることそのものがうれしいのだと思います。家が建つことが現実になるかどうかは問題ではなく、想像している現在の時間が貴重であり、かけがえのないものだと感じる一首です。
アルプスの五月の雪が赤羽のスーパーの棚であかるく光る
| 作者 | ユキノ進 |
| 歌集 | 『冒険者たち』 |



「アルプスの五月の雪」とは、ヨーロッパのアルプスから採れたペットボトルの水のことでしょう。そのペットボトルが、東京都北区に位置する赤羽のスーパーの棚に並べられています。そしてそれは明るく光っているのです。アルプスの水がアルプスで売られていたとしても特に面白くもありませんが、アルプスの水が赤羽で売られているというところに、面白さあるいは違和感を感じているのではないでしょうか。「あかるく光る」ことによって、かえってアルプスと赤羽のギャップが増しているようにも思います。「アルプス」「赤羽」「あかるく」とA音の頭韻が意識されているのかもしれませんが、読んでいて開放的な印象を感じさせてくれる一首です。
あなたへの供物のように澄んでいるくつぬぎ石は五月の庭に
| 作者 | 早坂類 |
| 歌集 | 『風の吹く日にベランダにいる』 |



靴を脱ぐための踏み台である「くつぬぎ石」。「五月の庭に」とあることから、縁側に設置されたくつぬぎ石を指しているのでしょうか。読みが難しいのが上句です。「あなたへの供物」はあなたへのお供え物ということですが、その「供物のように澄んでいる」と喩として用いられると具体的イメージがつかみにくく感じます。「澄んでいる」のはくつぬぎ石でしょうか。石が澄むという表現もあまり聞いたことがありません。したがって実景に即して論理的に読もうとするのではなく、上句の表現そのものを感じるように読むのがいいのでしょう。そのとき、「あなた」も「供物」も「くつぬぎ石」も「五月の庭」もすべてが「澄んでいる」と感じられるのではないでしょうか。漂う透明感、五月のさわやかな感じ、そして生と死の境界の消失など、とにかく澄みきった世界がここに提示されるような、そんな一首ではないかと感じます。
女ではまして春ではなき五月さらに夏でもなしと思いぬ
| 作者 | 小川佳世子 |
| 歌集 | 『水が見ていた』 |



「五月」と聞いて受ける印象は何でしょうか。寒くもなく暑くもなく、年の中でも気候はちょうどよく、好む人も多いでしょう。この歌は「五月」とは何かを考えている一首です。性別と季節を用いて五月を当てはめようとしていますが、まとめると「女」でも「春」でも「夏」でもないということになります。そうすると、その反面として、男で春と夏の中間というような五月が浮かび上がりますが、この歌ではあくまでも否定形の連続で詠われているだけで、男・春と夏の間を取り上げようとしているわけではありません。では、五月とは一体何なんだろうという、捉えどころのない想像だけが宙づりとなりますが、その宙づり感を素直に味わえばいいのだと感じる一首です。
早咲きのつつじ燃え立つ四阿で五月の分までキス繰り返す
| 作者 | 大田美和 |
| 歌集 | 『きらい』 |



「つつじ」といえば五月が見頃のイメージがありますが、「早咲きのつつじ」なのでそれより少し早い季節なのでしょう。「燃え立つ」から真っ赤な躑躅を想像します。「四阿」はどこかの庭園にあるものでしょうか、それともハイキングコースの途中の眺望のよい場所のものでしょうか。情熱的なのは下句で「五月の分までキス繰り返す」とあるので、あまり人目につかないところかもしれません。キスは一回ではなく、複数回、しかも五月の分までとなれば、相当長い時間キスをしていたのではないかと想像できます。真っ赤な躑躅と繰り返されるキス。四阿という四方が開放的な状況が、二人の燃え立つ様をどこまでも広げていくような、そんな印象を抱く一首です。
不本意といえど畢竟は瑣事ならん卯の花はじけて五月をこぼる
| 作者 | 大下一真 |
| 歌集 | 『即今』 |



卯の花とはウツギのこと。ウツギが五月に咲き誇っている様子を「はじけて五月をこぼる」と詠っているのだと思います。そのような季節において、主体は「不本意」なことがあると感じています。何に対する不本意でしょうか。ここでは何か特定の不本意をとりあげていっているのではなく、人生の節々に感じるすべての不本意についていっているのでしょう。「畢竟」は結局、「瑣事」は小さなことを意味します。通常不本意と感じることは、そのときの出来事だけに注目すれば不本意と感じて何か大きなことのように捉えがちですが、人生という視点からみれば、結局すべて些細なことなのです。そのように主体は感じているのでしょう。生きていれば、不本意と感じることも多々あるでしょう。でもそれら一つひとつを瑣事と捉えることができれば、随分と人生は生きやすくなるのではないでしょうか。
一縷といふもきれぎれとなり蒼穹へ雲雀のぼれり五月の雲雀
| 作者 | 雨宮雅子 |
| 歌集 | 『昼顔の譜』 |



「一縷の望み」などとよくいわれますが、「一縷」とは一本の細い糸すじであり、そのように細くかすかな事柄を意味します。主体には、一縷の望みのようなものがあったのでしょうか。その一縷でさえも「きれぎれ」となってしまっているのです。かなり厳しいというか、望みの薄い状態かもしれません。そのような状況において、蒼穹へのぼる五月の雲雀を見たのでしょう。五月の空へのぼる雲雀からは、上昇のイメージを受けます。きれぎれとなった一縷ではありますが、雲雀ののぼる姿から、その一縷はまだ完全には断たれていないことが窺え、わずかではあっても好転の兆しを感じます。雲雀の上昇とわずかな兆しが魅力的な一首です。
椎若葉押しわけて地にとどきたる五月のひかり踏みなずみけり
| 作者 | 島田幸典 |
| 歌集 | 『駅程』 |



椎の木の若葉が生い茂る五月。頭上には幾重にも重なる椎若葉が広がっているのだと思います。そんな中、主体は幾筋かの光が地上に届いているのを発見します。あふれる椎若葉に光のほとんどは遮られて地上には届いていない中、椎若葉の間を縫うようにして地上に届いた光。「押しわけて地にとどきたる」には、単に葉の間を抜けてきただけに留まらず、何とかして地上まで届こうとする光の意思のようなものを感じます。そのような光はどこか尊いもののように感じます。「踏みなずみけり」は、その表れであり、特別に感じる光だからこそ、踏むのを躊躇しているのでしょう。椎若葉を通って地に届いた「五月のひかり」の特別な感じがよく出ている一首ではないでしょうか。
降雹順位一位は五月 返礼に脚の短き一重虹顕つ
| 作者 | 大森益雄 |
| 歌集 | 『歌日和』 |



主体が詠っている場所に関していえば、一年の中で雹が最も降る月は五月ということなのでしょう。雹というと寒いイメージがありますが、新緑の季節のイメージが強い五月が最も多いというのも不思議な気がします。さて、雹が降った後に脚の短い虹が現れたのですが、五月の空に鮮やかに顕つ虹の姿が想像されます。「返礼に」という表現がポイントのひとつで、雹が降ることはどちらかといえばあまり望まれないことかもしれませんが、まるでありがたい贈り物をもらったような感じで虹という好まれる状況が現れた点が面白く感じられるのではないでしょうか。
磨きたる窓に五月の空ありてめまひのやうにわたしをさそふ
| 作者 | 小島熱子 |
| 歌集 | 『りんご1/2個』 |



窓をきれいに磨いたのでしょう。きれいに磨いたことで、その窓には五月の空がぎっしりを映っている様子がありありと迫ってきたのだと思います。窓を占める空を見ていると、主体は何かに誘われていくように感じたのですが、それが何かは表現されていません。しかし、その誘われ方は非常に危ういことだけは伝わってきます。それは「めまひのやうに」とあるからであり、きっかけとしての五月の空は窓という媒介を通すことで一層意識され、同時に眩暈を感じさせるほどの美しさだったのかもしれません。
ぐんにゃりと大型バスはゆがみつつ五月の凸面鏡を通過す
| 作者 | 中津昌子 |
| 歌集 | 『風を残せり』 |



この「凸面鏡」はカーブミラーのことでしょう。カーブミラーを車両が通過するとき、凸面という性質上、車両は歪められて見えます。特に大型バスであれば、車体が大きいため、カーブミラーにかなり接近して曲がっていったのだと思います。カーブミラーに近づけば近づくほど歪みの影響は大きく映し出されるでしょう。その様子が「ぐんにゃり」という言葉で端的に表現されています。五月という季節、曲がり角にはカーブミラーだけでなく、若葉があふれていたのかもしれません。ぐんにゃりと歪む光景の中にも、五月のさわやかさが滲み出ている一首だと感じます。
五月をシロと名付ければシロはいつまでもわたしの鼻をなめるんだ
| 作者 | フラワーしげる |
| 歌集 | 『ビットとデシベル』 |



物や生き物に名前をつけるのはよくあることですが、「五月」という季節に名前をつける行為は今まで聞いたことがありません。この歌では、まるで犬に名前をつけるように、五月を「シロ」と名づけています。そしてシロは「いつまでもわたしの鼻をなめる」のです。無理やり実景として捉えるならば、五月の風がわたしの鼻に吹き続けているようなイメージでしょうか。しかし、ここではそのような解釈をするのではなく、五月をシロと名づけたことにより、シロが躍動し出して、わたしの鼻をなめるという行為につながったことをそのままに受け取った方が面白いと思います。まるで犬が鼻をなめるように、シロが鼻をなめるのです。シロの元々は五月ですが、五月をシロと名づけることで生まれる変化そのものを楽しみたい一首です。
目覚めたら泣く夢ばかりつぎつぎに見せて五月の昼寝はこわい
| 作者 | 小俵鱚太 |
| 歌集 | 『レテ/移動祝祭日』 |



「五月の昼寝」という言葉だけを聞けば、気候もよく気持ちよさそうな気がします。しかし、この歌では、主体は五月の昼寝において「目覚めたら泣く夢ばかり」見せられているのです。一体どんな夢でしょうか。誰かに襲われる夢でしょうか、それとも大切な人が去ってしまう夢でしょうか。もちろん泣くような夢を見たいわけではないでしょうが、五月に昼寝をした後に目覚めたら、記憶に残る夢はいずれも泣く夢だったのです。「五月の昼寝はこわい」はストレートな気持ちなのではないかと思います。四月の昼寝や六月の昼寝であれば、結果は違っていたのでしょうか。五月の昼寝と限定されたところに実感がある一首です。
忘れ物に気づきてあつと口開けばわれを抜けたり五月の風が
| 作者 | 小島ゆかり |
| 歌集 | 『希望』 |



風を感じる瞬間はどんなときでしょうか。主体は忘れ物に気づいて「あつと」口を開いたとき、五月の風が口の中を、そして自分自身を抜けていく様子を感じとったのでしょう。それは口を開かなければ気づかない五月の風だったかもしれません。自分でも予期せず口が開いたことで、五月の風の存在を感じることができたのでしょう。意図して口を開けたのではないところがポイントで、忘れ物への気づきがもたらした体の反応が、体を抜けていく風を呼び込んだのだと思います。口を開けるという何気ない一瞬にも、自然を体感することができると感じさせてくれる一首です。
皐月の短歌
5月は5月でも、「皐月」という表現に関わる短歌を取り上げています。
宇治橋の陰は川面にとどまりて皐月の風にときおり揺れる
| 作者 | 江戸雪 |
| 歌集 | 『駒鳥』 |



京都府宇治市を流れる宇治川に架かる宇治橋。皐月の季節です。「影」ではなく「陰」であるところに、橋そのものがもつ暗さが表れています。宇治橋の陰が橋の下に見えますが、橋の陰であるため、橋が存在するところに生じるものであり、その場から離れることはありません。「川面にとどまりて」と表現することによって、陰自体が脇役ではなく主役になるような印象を受けます。そしてその陰はじっと静かなままではなく、揺れているのです。風が吹けば川面が揺れ、川面に映る陰も揺れることになります。動的な陰を感じることができ、印象に残る一首です。