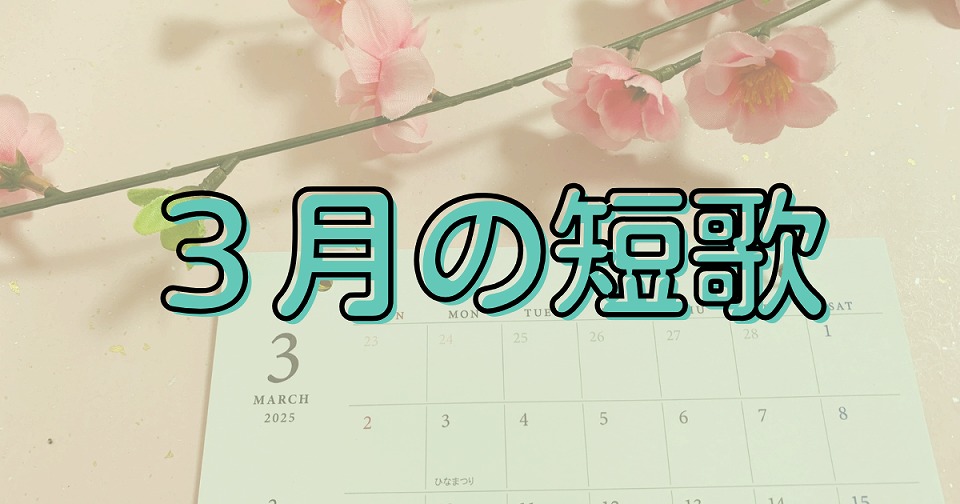「3月」に関わる短歌をピックアップしてみました。3月に詠まれたと思われる歌もあれば、別の月に詠まれている歌もあります。
3月の短歌
3月、三月、さんがつなどの言葉が含まれる短歌を取り上げています。
三月の海に花びら浮いていてこの水はさぞ冷たいだろう
| 作者 | 千種創一 |
| 歌集 | 『千夜曳獏』 |
 tankalife
tankalife真夏の海ではなく「三月の海」。まだまだ海の水は冷たいでしょう。その海に「花びら」が浮いているのを見つけました。花びらが浮いていることによって、その周辺の海が突如として立ち上がってくるように感じます。もし海に何も浮いていなければ、海面がずっと続くのみの海としての認識に留まりますが、花びらが浮くことで、花びらと海面との接触面がクロースアップされ、そこが海の手触りを感じる入口になってきます。その入口を通して「この水はさぞ冷たいだろう」が導き出されたのではないでしょうか。「三月」「海」「冷たい」とくれば、どうしても東日本大震災を想起してしまいますが、必ずしも直接的に結びつける必要はないでしょう。しかし、背景にはその出来事があるのかもしれないと感じてしまうところもあり、読み手がどう受け取るかにかかっているように思います。
三月の雨降る夜の水に濡れこんにやくも生身わが手も生身
| 作者 | 小島ゆかり |
| 歌集 | 『エトピリカ』 |



季節は三月、時間帯は夜、そして外は雨が降っている状況です。こんにゃくをボウルか何かに入れて、水にさらしている場面でしょうか。料理のためのあく抜きでしょうか。下句「こんにやくも生身わが手も生身」が触覚を伴った表現で印象深いです。こんにゃくの弾力のある感触、そしてこんにゃくを触っている自分の手の感触が次第に融合するような感覚を覚えます。媒介としての水が、こんにゃくと手との境界をシームレスにしていくような感じがします。その水は夜に降る雨とも呼応し、こんにゃくと手の感触が、徐々に三月の夜の外へも溶け出してしまいそうなイメージが膨らんでいきます。「生身」という表現が非常に生々しい感じがしますが、その表現によって触覚がさらに際立って感じられる一首になっているのではないでしょうか。
ときめきの心はかなし三月の光に白き桃の木木たち
| 作者 | 黒田淑子 |
| 歌集 | 『丘の外燈』 |



三月の太陽に照らし出される桃の木々を見ているところでしょうか。陽の光は、木の幹、枝、そして花びらにあたたかく当たっている様子が浮かんできます。桃といえばピンク色のイメージがありますが、ここでは白い花の桃が描かれ、白色光にも通じる陽の光の輝く様が伝わってきます。そんな桃を前にして、主体は「ときめきの心はかなし」と感じています。ときめきはプラスのイメージで捉えられることが多いと思いますが、儚いと感じてしまっています。ときめいても、たちまちにそのときめきが打ち砕かれることを想像しているのでしょうか。過去にもそのような経験があったのかもしれません。桃の木々も今この瞬間は鮮やかに咲き誇っていますが、季節が過ぎれば花も終わりを迎えます。「白き桃」の明るさが滲む歌ですが、明るければ明るいほど、ときめきの儚さに通じてしまうような印象のある一首だと感じます。
終電で関西弁にかこまれてどきどきしながら三月おわり
| 作者 | 永井祐 |
| 歌集 | 『日本の中でたのしく暮らす』 |



三月の末のことでしょう。仕事帰りか、遊びの帰りか、帰宅するのが終電になってしまった場面でしょう。終電には、関西弁を話すグループがいたのだと思います。「かこまれて」ということは、そこから抜け出せない、移動できない状況であり、この終電にはそれなりに乗客がいたため、他へ移ろうにも移れなかったのではないでしょうか。そこから離れることができれば「どきどき」することもなかったかもしれませんが、おそらく駅に着くまでは「かこまれて」いたため、乗車している時間をどきどきしながら過ごしたことが窺えます。しかし、この「どきどき」は嫌悪するようなどきどきではなく、むしろ興味深い方のどきどきだった可能性も想像できます。三月の終わりに関西弁に囲まれる、それもまた経験として楽しめるなら、この日をいつかまた思い出として語ることができるのではないでしょうか。
きみが息子の顔をしている三月の枯れた芝生を引き抜きながら
| 作者 | 山崎聡子 |
| 歌集 | 『青い舌』 |



「きみ」は夫でしょうか。枯れた芝生を引き抜いている「きみ」の顔を見つめている主体がいます。「きみ」の顔は、まるで「息子」のような顔をしているではありませんか。顔が似ているというのはもちろんですが、子がもつやわらかな印象の顔をしているということなのでしょう。大人の顔に子どもの顔を見るということ。それは主体が「きみ」の顔をそのように見つめたいという現れなのかもしれません。三月の枯れた芝生を引き抜く「きみ」は、普段の「きみ」の顔を見せずに無心に芝生を引き抜いている、そんな様子が浮かんでくる一首です。
三月の夕べは長し組織図から我の名を消し線でつなぎぬ
| 作者 | 吉川宏志 |
| 歌集 | 『雪の偶然』 |



会社か団体の組織図に名前が載るくらいですから、主体はある程度の役職を与えられていたことがわかります。退職することが窺えます。その組織図から、自分がいなくなった後の組織図をつくろうとしている場面だと思います。紙に印刷された組織図にペンで書き込んでいるとも採れますが、パソコンで組織図をつくりなおしているとも採れるでしょう。組織図の管理担当だったのかもしれません。三月でこの組織図は終わり、四月から新たな組織図が始まるのでしょう。自分の名前を消した後の位置に、代わりの者はしばらくいないのでしょうか。そこを空席として、自分の上にいる者と下にいる者を線でつないだ図が想像されます。組織図の自分の名前を自分で消すというのは、一体どういう心境なのでしょうか。「夕べは長し」に感慨深いものが感じられる一首です。
敷石がはがれて空がみえとるとおもうたら三月のみずたまり
| 作者 | 吉岡太朗 |
| 歌集 | 『世界樹の素描』 |



雨上がりの場面です。庭の敷石でしょうか。敷石の並んでいるあたりを見ると、雨上がりの空が見えているではありませんか。見ているのはもちろん地面なのですが、そこに空が輝いているのです。主体は見た瞬間、敷石のうちの一枚が剝がれて、空が現れたと感じたのでしょう。しかし、よくよく冷静に考えてみれば、それは敷石が剝がれたわけではなく、水たまりがそこにできて、その水たまりが空を映していたということがわかったのです。勘違いというか、錯覚というか、そのような歌だといえばその通りなのですが、この歌が活き活きと感じられるのは関西弁によるところが大きいのではないでしょうか。「みえとる」「おもうたら」に、本当にそのように見えた、本当にそのように思ったというリアルさが伝わってくるようです。関西弁の魅力が歌に活きた一首ではないでしょうか。
くたくたのセーターのまま、昼間まで眠っていたと、三月は来る
| 作者 | 野口あや子 |
| 歌集 | 『眠れる海』 |



主体はセーターを着ています。起きた日の前日は、そのセーターがくたくたになるようなことを行っていたのかもしれません。あるいは、昼間まで眠っていたことで、寝ている間にセーターがくたくたになった可能性もあります。その両方かもしれません。さて、昼間まで眠っていて起きたとき、「三月は来る」状態になっていたのです。「眠っていたと、」の「と、」の採り方が非常に難しいのですが、「三月」を擬人化してみると「と、」は割とすんなり受け入れられるのではないでしょうか。客人が自分の家にやってくるように、擬人化された「三月」が自分の家にやってきた。眠りについた前日は二月最後の日で、昼間に起きたこの日は三月一日だったとすれば、眠りがあければ三月になったということで筋は通ると思います。ただ、この歌の詠い方からして、読み切れていない何かが隠されているようにも思います。そして、その何かがある方が、謎めいていて魅力が増すように思いますが、いかがでしょうか。
三月の深夜ラジオのDJの「またどこかで」は別れの言葉
| 作者 | 伊波真人 |
| 歌集 | 『ナイトフライト』 |



これまで続いていた深夜ラジオが、番組編成のためか、三月で終了する場面でしょうか。その放送の最終回の最後の最後、DJは「またどこかで」と口にして、番組は終わったのだと思います。「またどこかで」は、文字通りに捉えれば、またどこかで会いましょうということになりますが、実際はそうではありません。「別れの言葉」とある通り、「またどこかで」はもう二度と会えないことがわかった上で放たれた言葉なのだと感じます。DJにとっても、リスナーにとっても、もうこの番組が復活することはなく、再び番組で会うことはないとわかっているのではないでしょうか。それでも最後の言葉は「またどこかで」なのです。この一言が重たく響くのは、この深夜ラジオがずっと継続されてきたことの証なのかもしれません。
なぜ自分は無傷なのかとおもふとき三月の空また雪が降る
| 作者 | 林和清 |
| 歌集 | 『去年マリエンバードで』 |



「自分は無傷」、裏を返せば自分ではない誰かは無傷ではないということでしょう。他者は傷を負っているのに、自分はその傷を負っていない側にいることに対して、いたたまれないというか、納得できないというか、自分の中で消化しきれない気持ちがあふれているのでしょう。この傷が何なのかは明確に示されていません。しかし、傷を負った者と自分の無傷を思うとき、三月の空に雪が降っていたのです。「また」ということは、過去にも降った日があるということです。「また」はいつに対しての「また」なのでしょうか。東日本大震災が起きた日にも雪が降ったようです。「三月の空また雪が降る」からは、主体は東日本大震災の日を思い出しているのかもしれません。多数の傷を負った者に対して、自分が無傷であることを問わずにはいられなかったのではないでしょうか。この上句はとても重たく響く問いかけに感じる一首です。
三月の風花はつかきらきらし親しみやすき神経科へ行く
| 作者 | 渡辺松男 |
| 歌集 | 『歩く仏像』 |



「風花」とは晴天に降る雪のこと。風花が三月に舞っていて、わずかにきらきらと輝いている光景です。さて、風花の舞う中、主体は神経科を訪れたのです。ポイントは「親しみやすき」であり、この言葉が用いられていることで、歌が輪郭をもって急に立ち上がってくるように思います。親しみやすいのは、神経科で勤務する医師や看護師が付き合いやすい人だからでしょうか。それとも、神経科という場所そのものが主体にとっては親しみやすいものなのでしょうか。元々神経科に通わなくて済むなら、通わずにいるのでしょうが、主体はやむなく神経科に通っているのでしょう。何度も通えば、神経科へいくことも「親しみやすき」となるのでしょうか。三月の風花が、神経科へいくことを後押しするような一首で、どこか明るさを伴った歌だと感じます。
日曜はお父さんしている君のため晴れてもいいよ三月の空
| 作者 | 俵万智 |
| 歌集 | 『チョコレート革命』 |



「お父さん」=「君」、つまり「君」は誰か別の家族の「お父さん」でもあるのです。主体は「君」と深い関係にあるのでしょうが、日曜日は「君」と会えずにいます。それは「君」が「お父さん」をしているからです。「晴れてもいいよ三月の空」とあり、「君」が「お父さん」でいるときも、「君」のためを思っていることが伝わってきます。そして「晴れてもいいよ」の「いいよ」が絶妙だと感じます。必ず晴れてほしいと願うわけでも、逆に雨が降ってほしいと願うわけでもありません。どちらかに極端な場合、晴れ過ぎると癪ですし、大雨だと可哀想に感じてしまうかもしれません。ですから「晴れてもいいよ」はちょうどよく、また余裕が感じられるではありませんか。隔たった場所から「君」のことを思っている様子が、ゆったりとした三月の空に重ね合わさる、そんな一首ではないでしょうか。
三月の浅間の肌は黒白にきりりと締まり雲を払へり
| 作者 | 春日いづみ |
| 歌集 | 『地球見』 |



長野県と群馬県の境に位置する浅間山ですが、三月の浅間山を詠った歌です。「黒白」とありますが、山裾付近は黒く、山頂付近は雪のため白く見えている状態を指しているのでしょうか。「黒白」ではなく「黒白」という読み方が、三月の空気に引き締まった感じをよく表していると思います。その引き締まって屹立する様子は、山にかかる雲をも払いのけ、浅間山の雄大な姿を余すところなく見せてくれるのではないでしょうか。「きりり」はありがちなオノマトペかもしれませんが、引き締まった浅間山を表すのにぴったりな表現のようにも思います。
3月に花咲くという球根を植えれば
すこしおちつくこころ
| 作者 | 今橋愛 |
| 歌集 | 『としごのおやこ』 |



3月に花が咲く球根の植物といえば、チューリップやヒヤシンスなどが想像されます。秋ごろに植えたのでしょう。植え終わって主体の心は少し落ち着いたようです。元々心が落ち着いていなかったから球根を植えることにしたのか、植え終わったことで自分の心が落ち着いていなかったことに気づいたのか、どちらでしょうか。どちらとも判断できかねますが、植えたことで心が落ち着いたのは確かです。球根というのもよく、土の中にしっかりと位置を確保していて安定感があり、「おちつくこころ」に通じるものを感じます。実はこの歌は、流産を詠った歌群の中の一首です。そういう背景を想像しながら読むと「おちつくこころ」とはいいながらも容易ならざる深さが一層伝わってきます。開花までの時間、心は穏やかさを保ち続けることができるのかどうか。印象深い一首です。
三月に増え続けたる写真立て捨てたし風呂が沸くまでの間に
| 作者 | 染野太朗 |
| 歌集 | 『あの日の海』 |



三月に写真立てが増え続けるのはなぜでしょう。やはり卒業や別れのシーズンに重なるからでしょうか。これまでのいくつもの三月が訪れる度に、主体は記念写真をもらってきたのかもしれません。「増え続けたる」には、自分で積極的に増やしていったというのではなく、誰か他者からもらったという印象を受けます。徐々に増えていった写真立てをふと捨てたくなったのでしょう。理由が明確にあるようにも思えません。明確な理由はないけどふとそう感じる瞬間というのがあるのではないでしょうか。「風呂が沸くまでの間に」というところが、突如として捨てたい気持ちに駆られた様をよく表しているように思います。記憶や記録は余計な思考を生み出すことがありますが、それらを一旦整理してすっきりとしたい、ひょっとするとそんな思いがあるのかもしれません。
空瓶のあまた並びているところ愁いをおびし三月の雨
| 作者 | 岡部桂一郎 |
| 歌集 | 『一点鐘』 |



空瓶がたくさん並んでいるのは、外でしょうか、それとも家の中でしょうか。どちらもあり得ると思いますが、ここでは外をイメージしました。瓶回収のゴミの日に、色別に瓶が並べられている様子を想像しました。三月の雨がそれら空瓶に降り注いでいるのでしょう。その光景を見て主体は「愁い」を感じているのです。空瓶そのものから愁いが発せられているというよりも、主体の中に、愁いの種があり、空瓶を見る行為を通して愁いが顕在化したということではないでしょうか。未開封の中身の詰まった瓶ではなく、空の瓶が多数並んでいることが愁いの発動に一役買っているような感じです。ひとつではなく多数あるところもポイントで、雨に濡れる空瓶の光景が印象的な一首です。
三月のバラのつぼみの先端のひらかぬ内に雨降り終わる
| 作者 | 永田淳 |
| 歌集 | 『1/125秒』 |



降り続けていた三月の雨が止んでしまいました。普段気にかけていたバラでしょうか。そのバラのつぼみの先端を見てみると、まだつぼみは開いていないようです。バラの開花が待ち遠しい様子も感じられますが、この日は開かないままでした。しかし、開かなかったことが残念で仕方ないというわけでもなさそうです。自然は自然としてあるので、バラの開花の時期もしかるべきときに訪れるのであって、そのままに受け入れようという感じではないでしょうか。「三月」「バラ」「雨」とあれば、正岡子規の歌〈くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる〉が何となく思い出されますが、ひょっとすると背景にあるのかもしれません。
三月が味気なく過ぎ気がつけば人を見るのが億劫である
| 作者 | 花山周子 |
| 歌集 | 『屋上の人屋上の鳥』 |



生きている以上、好き嫌いによらず、人と関わらなければならない場面も出てきます。人と関わる機会をできるだけ減らすことはできるでしょうが、皆無にすることは難しいでしょう。人と関わることを避けることができない状況において、「人を見るのが億劫」と感じることは、生きづらさにつながっていくかもしれません。この三月は特に何か目立ったこともなく過ぎ去ってしまったようです。そして自分でも意図していなかったのですが「人を見るのが億劫」に感じている自分がそこにいるのです。そう望んだわけではないけれど、そう感じざるを得ない自分がいるのだから仕方ありません。いずれこの「億劫」は解消されると思いますが、「億劫」だと感じるときは、一旦人からできる限り離れて過ごすのもひとつの手かもしれません。自分の気持ちが正直に吐露された一首で印象に残ります。
話し足りないように降る三月の雪に離陸をはばまれており
| 作者 | 中沢直人 |
| 歌集 | 『極圏の光』 |



飛行機に乗って、ここではないどこかへ旅立とうとしている場面でしょう。しかし、三月の雪が降っており、中々離陸することができません。その雪は「話し足りないように」降っているのです。まだまだ話していないこともあるし、もっともっと話したいから、出発するのをちょっと先延ばしにしてはどうかなといった感じでしょうか。主体も早く出発したい気持ちはもちろんあるのですが、出発元である現在のこの場所への思いもあるでしょう。少しくらい離陸が遅れても、そんなに問題はないのかもしれません。離陸しないことに対するイライラはほとんどないでしょう。むしろ、話し足りないように降る雪をやさしく見つめる目を感じる一首です。
魚偏に雪の魚のほろほろと身のほぐれつつ三月よ来い
| 作者 | 藤島秀憲 |
| 歌集 | 『すずめ』 |



三月を待ち遠しく感じている様子でしょうか。「三月よ来い」に力強さが感じられます。「魚偏に雪の魚」は「鱈」です。鱈を味わっているのでしょうが、その身がほろほろとほぐれている状況が丁寧に詠われています。鱈といわずに、あえて「魚偏に雪の魚」というところがポイントで、このように音数をかけて展開されることで「雪」と「魚」の存在感が両方とも立ち上がってくるのではないでしょうか。鱈という一字二音では見過ごしてしまいそうになる手触りがここにはあり、結句の「三月よ来い」につながっていく流れがスムーズに感じられる一首だと思います。
噴水はこころをわたしは肉体を殺して三月に立ちすくむ
| 作者 | 大森静佳 |
| 歌集 | 『ヘクタール』 |



「噴水」と「わたし」、「こころ」と「肉体」が対比的に描かれています。噴水はこころを殺し、わたしは肉体を殺したのです。詰まるところ、こころも肉体も殺されてしまったわけです。このこころと肉体は、一体誰のものを指しているのでしょうか。やはり自分自身でしょうか。その自分は「わたし」と同一なのでしょうか。そもそも噴水にこころを殺すことができるのでしょうか。噴水が直接的にこころを殺したのではなく、噴水に対するわたしの記憶がこころを殺したのかもしれません。肉体を殺すとは文字通り殺したのでしょうか。ともかく、こころを殺されたわたしは、肉体を殺さざるを得なかったのです。そして、三月に立ちすくむのですが、ここで立ちすくんでいるのは一体誰なのでしょう。やはり、わたしなのでしょうか。考えれば考えるほど、疑問ばかりが湧いてくる歌ですが、殺されたはずのこころと肉体の輪郭と手触りがいつまでも残り続けるような一首だと感じます。
行き先を知らないバスがカレンダーの三月で扉を開けている
| 作者 | 我妻俊樹 |
| 歌集 | 『カメラは光ることをやめて触った』 |



カレンダーの三月の写真にはバスが選ばれているのでしょう。そのバスの行き先を主体は知りません。行き先はもとより、そもそもそのバス自体を知らない可能性もあります。特に都市部ではないあまり知られていない地域を走るバスであれば、知っている人の方が少ないかもしれません。そのバスを知っているのは、この写真を撮影した人か、このカレンダーづくりに関わった人たち、そしてこのバスを普段利用している人たち、あるいはバス好きの人たちでしょう。とにかく、目の前のカレンダーに写るバスは扉を開けている状態なのです。扉を開けているので停車中なのでしょう。停留所でしょうか、客は乗り降りしているのでしょうか。読み手は色々と想像できますが、主体にとっても「行き先を知らない」がゆえに、そのバスの行方をさまざまに想像することができるでしょう。扉が開いているという開放感が、行方の想像を制限しない様と重なるように感じられる一首です。
白い帆のように三月、君はまた何かを言いまちがえて微笑む
| 作者 | 服部真里子 |
| 歌集 | 『遠くの敵や硝子を』 |



「白い帆」は船やヨットの帆のイメージでしょうか。これからの旅立ちを想像させてくれますが、その白い帆をもった船のように三月があるということなのでしょう。「ような」ではなく「ように」なので、そのように感じます。そして「君」は微笑んでいます。それは単純に楽しいから、うれしいからというのではなく「何かを言いまちがえて」しまったからです。これまで何度も言いまちがえてきたことがあったのでしょう。そして今回も。主体はその言い間違いが初めてではないことを知っています。「君」は言い間違えたことを照れているのでしょうか。いや、間違えてもいいと思っているのでしょう。言い間違うことが二人の関係性の中で、何か特別な意味をもちはじめているのかもしれません。それは微笑みに通じるような関係性です。言い間違いがなくなるとき、この三月も、二人の関係性も失われてしまうのかもしれない、そんな印象を受ける歌ではないでしょうか。
三月は七十代の一年生さつそくに傘置き忘れたり
| 作者 | 池田はるみ |
| 歌集 | 『亀さんゐない』 |



この歌を含む一連の題は「三月生まれ」。三月生まれの主体は、この三月で七十代になったのでしょう。七十代初の三月はまるで「一年生」のようだということです。一年生になったばかりの行動の結果として、傘の置き忘れが示されています。傘を置き忘れるということは、別に七十代に限らず、何歳でも起こり得ることで、これまで経験した人も多いでしょう。しかし、ここでは「さつそくに」が効いており、節目の三月に早速置き忘れた点に注目したいものです。早速傘の置き忘れをしてしまったということは、今後続いていく日々に一体どれだけの失敗(と感じられるようなこと)をしていってしまうのだろうか、という気持ちが芽生えていないといえば嘘になるでしょう。しかし「さつそくに」には若干の余裕も感じられます。今後も傘の置き忘れぐらいで済めば、それはそれでいいのかもしれず、ある程度そのような失敗は起こるものだと想定していれば、その失敗も受け入れながら生きていくのが七十代なのかもしれないと感じられる一首です。
さんぐわつのつごもりの夜の大いなるうつろを盈たすしだれ桜よ
| 作者 | 沢田英史 |
| 歌集 | 『異客』 |



「つごもり」とは月末のこと。三月末の夜、しだれ桜を見ているところでしょう。ライトアップされた桜でしょうか。「大いなるうつろ」をどう捉えるかですが、三月末の夜の空間にがらんどうになった部分があると空間的に捉えるのか、それとも心の状態としてのうつろ、つまり心理的な面として捉えるのか、ここは読みのわかれるとことかと思います。空間的に捉えた場合、下から見上げるしだれ桜は夜空にしっかりとした存在感を示すでしょうし、まさに夜空のうつろを埋めている印象があるでしょう。一方、心理的に捉えた場合、主体にとってこのしだれ桜が心を盈たしてくれるものとして、タイミングといい、存在の大きさといい、充分すぎるほど合致したのではないでしょうか。明日から四月に変わり、新たな年度が始まるわけですが、この日に「うつろ」が盈たされたことが大きいのかもしれません。
三月の雪ガラスごしに吹き上がり音なき朝の円舞曲きく
| 作者 | 小島なお |
| 歌集 | 『乱反射』 |



「円舞曲」とはワルツのこと。三月の雪が窓の外に降っています。その雪は上から落ちているのではなく、風に吹かれて窓ガラスを下から上に吹き上がっているのです。窓の内側から外を見ている光景でしょうが、雪の吹き上がりに音はありません。音はなくただ雪だけが無音で見えているのです。しかし、その景に主体は円舞曲を聴いてしまったのでしょう。それは室内に音楽が実際に流れているわけではありません。想像の世界において、円舞曲が流れ出したのです。テンポのよい円舞曲が軽やかに頭の中を流れていく様子は、雪の舞う景色からもたらされたものですが、同時にこの円舞曲は再び外の雪の景色へ伝わっていくのではないでしょうか。窓の外の雪の光景と、円舞曲とが互いに関係しあう、そんな一首ではないでしょうか。
いくたびも三月は来てそうやって人の背丈を忘れてしまう
| 作者 | 笠木拓 |
| 歌集 | 『はるかカーテンコールまで』 |



一年は十二ヶ月。三月は一年ごとに訪れます。自分が生きている間に訪れる三月は、多くても百回程度でしょうが、人類の長い歴史において訪れる三月は何度も何度もあることでしょう。さて、主体は三月が来るたびに「人の背丈を忘れてしまう」ようなのです。いや、正確には三月が来て「そうやって」とあるので、毎度訪れる三月のたびに同じ程度に人の背丈を忘れてしまうのではなく、回数を重ねれば重ねるほど、だんだんと忘れてしまう度合いが強くなるといった感じでしょうか。最初は何となく覚えていた「人の背丈」も、三月が幾たびも訪れることで、もう思い出すこともできないくらいに忘れてしまっていくのでしょう。記憶の風化といえばそれまでですが、忘れていかないようにする手立てはないのでしょうか。そもそも忘れないようにする手立てを構築する必要性があるのかどうかもこの状況だけでは不明です。忘れていくことが自然な場合もあるでしょう。しかし、この歌の「人の背丈」は忘れたくはない、忘れてはいけない何かのように感じずにはいられません。
三月の木立はゆらぐ過ぎてゆく日をつまらなく転がすように
| 作者 | 安田茜 |
| 歌集 | 『結晶質』 |



三月の木立が揺らいでいます。その揺らぎ方に「過ぎてゆく日をつまらなく転がすように」という様子を見い出しています。各日は日々過ぎてゆくわけですが、三月の木立がその日々を転がしているようだというのです。しかも「つまらなく」転がしているようだと。木立自身がつまらなく感じているのでしょうか。そうではないと思います。主体が、過ぎてゆく日をつまらなく感じているのではないでしょうか。主体がそう感じているからこそ、木立の揺らぎ方につまらなさを見い出してしまったのでしょう。主体が楽しく日々を送っていれば、木立の揺らぎにも楽しさを見い出していたはずではないでしょうか。木立を見たときの主体の日々には、つまらなさを感じる部分があったのだと思います。つまらなさは今度どのように変化していくのか、そのあたりも気にかかる一首です。
三月の大気は髪に重けれど地にこもりゐる声聞かむとす
| 作者 | 水沢遙子 |
| 歌集 | 『空中庭園』 |



地上で生きている我々は、普段意識しているわけではありませんが、気圧に圧されながら生きているのです。三月の大気がふと髪に重たいと感じたのでしょう。そのように大気は上方から下方へ向かい、垂れこめているわけですが、主体はそのような三月のある日において、「地にこもりゐる声」を聞こうとしたのです。では、地にこもりゐる声とは何でしょうか。これははっきりとはしませんが、地中に眠る数多の生命の声のようなものかもしれません。この歌の収められている一連の題が「有馬高槻断層」です。地中に対する意識の強さが感じられますが、断層という長い年月を経て形成されたものへも積極的に耳を傾けているのではないでしょうか。
蝸牛は生きてゐるのか抜殻か草生に白し三月のあめ
| 作者 | 石川不二子 |
| 歌集 | 『ゆきあひの空』 |



かたつむりの動きは非常にゆっくりとしているので、生きているのか、死んでいるのか、抜け殻なのか、パッと見ただけではわからないことがあります。それにしても、かたつむりにはやはり雨が似合います。草生に降りそそぐ三月の雨が白さを伴って立ち込めるような情景でしょう。雨の中にあるかたつむりは、主体の目からはもはや生きているのか抜け殻か区別がつきません。そして、どちらであるかをはっきりさせようとしているわけでもありません。生きていようが、抜け殻であろうが、かたつむりがそこにあるということだけは確実なのです。そこにあるかたつむりに雨が降っている、もうそれだけで充分自然の恩恵が満ちあふれていると感じられるのではないでしょうか。
三月の雪ふる夜にだす手紙ポストのなかは温かですか
| 作者 | 杉﨑恒夫 |
| 歌集 | 『パン屋のパンセ』 |



三月の夜、雪が降っている状況で、まだまだ寒い時期です。主体は手紙を出すために、ポストへ向かったのでしょう。手紙をポストに投函したとき、ふとこう思ったのです。「ポストのなかは温かですか」と。ポストの外側は外気に触れて寒いかもしれませんが、ポストの内側は直接外の空気に触れるわけではないため、温かいかもしれません。投函口だけが空気の出入りを若干許すくらいでしょう。しかし、ポストの中の温かさを確かめる術がありません。投函口から手を奥まで突っ込むことも難しいと思います。そうなれば、後は想像するのみです。温かいだろうか、きっと温かいのだろうな、温かい状態であってほしい…。「温かですか」という、やや約まったようないい方が、却って味わいを感じさせ、やわらかさとやさしさをもった問いかけになっているように感じます。
猛禽の青きむくろがさんぐわつの陽射しに特別扱ひされる
| 作者 | 吉田隼人 |
| 歌集 | 『忘却のための試論』 |



猛禽といえば、鷲や鷹などが思い浮かびます。死んでしまった猛禽が、三月の陽射しに晒されている場面でしょう。本来猛禽は鋭い爪や嘴をもっており、獲物を捕まえる側の存在ですが、そのような一見強者である側の鳥が死んでいるところに、もうそれだけで何か特別な感じが漂います。「特別扱ひされる」というのをどう捉えるかということですが、やはり猛禽だから特別であるというイメージでしょうか。捕食される側の鳥の骸があったとしても、それほどの違和感を覚えませんが、捕食する側の鳥の骸を見たとき、なぜなのだろうという違和をそこに覚えてしまうのではないでしょうか。特別扱いしているのは陽射しではなく、それを見ている人間の側なのかもしれませんが、三月の陽射しに強烈に浮かび上がってくる「猛禽の青きむくろ」がインパクトを残していく一首だと感じます。
透明な傘がわたくしをむき出しのままに庇護して 三月の雨
| 作者 | 小島熱子 |
| 歌集 | 『ぽんの不思議の』 |



三月の雨の日のことです。透明なビニール傘を差して外を歩いているところでしょうか。傘で雨を凌いでいるのですが、透明な傘であるために自分が「むき出し」の状態になっているように感じられるのでしょう。もちろん傘で防いでいるため、直接雨が体に当たるわけではありませんが、透明ではない傘に比べて、自分自身が雨に晒されているように感じるのかもしれません。一応傘なので、守られてはいますが、透明な一枚の膜を隔てているだけであり、それは何かのきっかけでたちまち崩れ去ってしまうような危うさを伴った「庇護」なのかもしれません。透明な傘であるがゆえに、一層「わたくし」自身が外界へ露出してしまう、そんな印象を受ける一首です。
カレンダーにクレーの線が伸びてゐる三月は水曜からはじまる
| 作者 | 河野美砂子 |
| 歌集 | 『無言歌』 |



「クレー」とは、スイス出身の画家パウル・クレーのことでしょう。クレー単独のカレンダーでしょうか、あるいは偶々三月だけクレーの絵が掲載されたカレンダーでしょうか。いずれにしてもカレンダーの三月のところにはクレーの絵が載っているのです。クレーの絵というと色彩の美しさの印象がありますが、ここで主体は、その絵にクレーの線の伸びを見ています。「三月は水曜からはじまる」は何ていうことのない表現ですが、この下句がとても魅力的で、このときの感情や一回限りの状況を強調しているように感じます。毎年三月が水曜から始まるわけではありませんし、かといって他の年は違う曜日ばかりから始まるわけでもありません。水曜から始まる年は他の年でもありますが、クレーの線に魅せられ、三月が水曜から始まることをこの日に感じたことは、やはりこの日以外は味わうことのできないものなのだと思います。
駅前にまだ点りゐる三月のイルミネーションなにを祝つて
| 作者 | 山木礼子 |
| 歌集 | 『太陽の横』 |



街中のイルミネーションは大抵冬の時期に設置されることが多いでしょう。特にクリスマスまでに点灯式が開催されるケースがほとんどではないでしょうか。ここでは三月にもなってまだイルミネーションが点っている駅前の様子が詠われています。イルミネーションが何かを祝うものであるとすれば、クリスマスや年末年始を祝うものとして飾られているケースが多いでしょう。その意味において三月のイルミネーションはあまりにも季節外れに感じられます。「なにを祝つて」にその思いがよく表れているでしょう。しかし、三月のイルミネーションが単に片づけ忘れられているのではなく、クリスマスや年末年始以外に本当に何かを祝うために点っているのだとしたらどうでしょうか。三月にイルミネーションが点っているという事実に対して、想像を膨らませてみることも今日一日に刺激を与えてくれる一コマとなるのではないでしょうか。
四辻の南へ向かう道だけが明るし、三月下旬の未練
| 作者 | 島田幸典 |
| 歌集 | 『no news』 |



今まさに四辻に差しかかったところなのでしょう。東西南北に道は延びていますが、「南へ向かう道」だけが明るいようです。太陽の位置の関係でしょうか。それとも、四辻にはビルが立ち並んでおり、ビルや建物の配置や高さの加減で、東・西・北の道は暗く感じられるのかもしれません。明るさを求めるのであれば、この場合南へ向かうことになるのですが、ことはそう単純ではなさそうです。「三月下旬の未練」があるからです。未練が何かはこの歌では書かれていませんが、この歌の一連からすると人間関係のように思います。東西南北という方角を考えた場合、やはり東・西・北のいずれかに、この未練があるということなのではないでしょうか。これから、南の明るさへ向かうとしても、振り返れば、南ではないところに未練が感じられるのです。それはこれまで過ごしてきた時間を帯びているからもしれません。四辻という、四方向が明確に示される場所であるがゆえに、明るさおよび未練がくっきりと意識されるのだと思います。表記でいえば「四辻」の「四」、「三月」の「三」という数字の関連も面白く感じられる一首です。
キャリーバッグ見ては「東京からすらも逃げるの」と問いし二〇一一年三月
| 作者 | 川島結佳子 |
| 歌集 | 『感傷ストーブ』 |



2011年3月のこと。主体は東京に住んでいたのでしょうか。誰かがキャリーバッグをもっているところを見た状況だと思います。2011年3月といえば、東日本大震災が発生した月です。そのときのことを思い出しているのでしょう。被害の大きかった東北からは、西の方へ非難する人もいました。東京でキャリーバッグを見たとき、主体は「東京からすらも逃げるの」と心の中で問いかけたのでしょう。キャリーバッグをもっている人が本当に逃げるのかどうかはわかりません。それでもその問いが浮かんできたのです。それは素直に表出した問いかけに感じます。とここまで思ってきたのですが、キャリーバッグをもっていたのはひょっとして主体自身だった可能性もあると感じました。自分のキャリーバッグを見て問いかけている、そう採れなくもありません。誰のキャリーバッグなのかの判断がいまだにつきかねるところですが「東京からすらも逃げるの」の問いは非常に鋭く、そして重く、この三月に突き刺さっていることだけは確かに感じます。
他人には発見されぬひとがたのしろきかたちで三月を行く
| 作者 | 荻原裕幸 |
| 歌集 | 『リリカル・アンドロイド』 |



三月の街を歩いているのでしょうか。面白いのは「他人には発見されぬひとがたのしろきかたち」というところです。「他人には発見されぬ」ですから、他の人からは見つからないような姿ということでしょう。「ひとがた」とあるので、人間の輪郭は保っているようです。「しろき」なので、あれこれ雑多な色が混在している状態ではなく、白一色のイメージです。これらは現実的な姿というのではなく、現実から離れた想像の世界における姿なのではないでしょうか。透明人間のようなイメージを浮かべてもいいのですが、「しろき」とあるので少し違うように思います。もう少し捉えどころのないイメージといいますか、霞や霧のような状態が思い浮かんできます。確かにそこにあるのですが、具体的に捉えられない感じが、霞や霧のイメージと重なります。主体自身の心境として、わたしは今他人からは発見されない姿で歩いていますよといった感じでしょうか。捉えどころのない姿でいる様子を存分に想像して味わいたい一首です。
諦めてない、といふ嘘 三月のひかりの幹を水は奔らむ
| 作者 | 魚村晋太郎 |
| 歌集 |



三月の陽に木の幹が照らされています。その幹の中を地中から各枝に向かって水が奔っているのです。本当は「諦めてない」と主体はいいたいのでしょうが、それは嘘だということもわかっているのです。つまり、すでに諦めているのです。では、なぜ「諦めてない」というのでしょう。強がりでしょうか。心の底からの希望としては、諦めたくはないのでしょう。しかし、諦めるという結果の方が勝っているのです。何としてでも諦めないという強い意志はもはやそこにはないのかもしれません。このとき「諦めてない」は表面的な思いに留まります。それはまるで、幹の樹皮には光が当たって輝いているように見える一方、幹の中では水が涼し気に流れている様子に重なります。その水にもう熱量はありません。淡々と現実を受け入れて生きていく。そういうことなのかもしれません。幹を見つめる主体の眼差し、そして嘘だと吐露した気持ちに寄り添いたい一首です。
弥生の短歌
3月は3月でも、「弥生」という表現に関わる短歌を取り上げています。
ふくふくと中国茶のむ昼下がり弥生は桃の点心がよし
| 作者 | 松平盟子 |
| 歌集 | 『うさはらし』 |



弥生の昼下がりに中国茶を飲んでいる光景ですが、「ふくふくと」のオノマトペがいいですね。慌てず騒がずゆっくりとした時間が流れているように感じます。弥生ですから、桃の花の咲く季節でもあり、そこから「桃の点心」につながっていきます。「桃の点心がよし」に、穏やかで幸せなひとときを感じることができるのではないでしょうか。桃の点心を食べながら、中国茶を味わう。何と素敵な時間でしょうか。大きなイベントはなくとも、日々にこのような味わい深い幸福を感じられるかどうか、それが人生の充実につながっていくのだと思います。
しろじろといずくの空を鷗どり弥生は水のたゆきうすにび
| 作者 | 高倉レイ |
| 歌集 | 『薔薇を焚く』 |



鷗が空を飛んでいるのでしょうが、「いずくの空」とある通り、不定の空を指しているところから、遠くの空を飛んでいる状態をイメージすればいいでしょうか。白々と見えているのだと思います。あるいは想像の中の鴎でしょうか。どこかの空を白々と飛んでいる様を思い浮かべているのかもしれません。空を飛ぶ鷗とは対照的に、下句では地上の「水」、おそらく海や川や湖などの水面が思い起こされます。「たゆき」は「弛し」の連体形で、ぼんやりとした様を意味しています。そして「うすにび」とは薄鈍色、つまり薄い灰色のことです。したがって「たゆきうすにび」とはぼんやりとした薄い灰色のことで、弥生の水面はそのように感じられたということでしょう。景を重視した一首ですが、「しろじろ」「いずく」「たゆき」「うすにび」など平仮名で展開されるこれらの言葉の選択が美しく、そこにひとつの世界が立ち上がってくるように感じます。
マカロンの繁殖期である弥生にはころんとしあわせが転がっている
| 作者 | 九螺ささら |
| 歌集 | 『ゆめのほとり鳥』 |



弥生の季節は「マカロンの繁殖期」であるようです。ここでいう繁殖期とは、マカロンがよく売れ、店頭に多数マカロンが並んでいるといった状態を指していると思います。「ころんとしあわせが転がっている」は、一見ありふれた表現のような感じもしますが、これはこれで読むととてもいいなと感じます。「マカロン」と「ころん」の音の類似性が、また「ころん」と「転がっている」のK音の共通性がその効果を上げているでしょう。マカロンの小ささと、それがころんと転がるような様子が、マカロンの鮮やかな色合いとともに映像として現れてくる一首です。