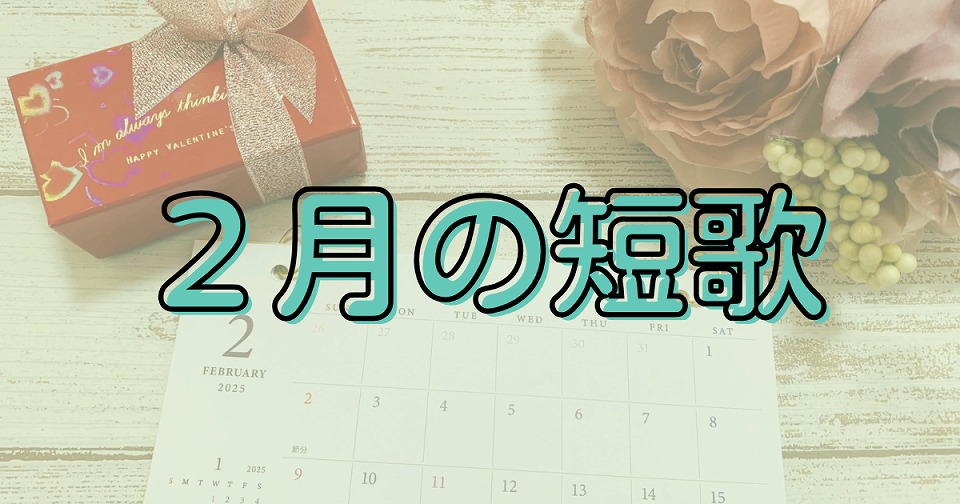「2月」に関わる短歌をピックアップしてみました。2月に詠まれたと思われる歌もあれば、別の月に詠まれている歌もあります。
2月の短歌
2月、二月、にがつなどの言葉が含まれる短歌を取り上げています。
ポケットを空にしたのにもう二月なのに歩けばまだ何か鳴る
| 作者 | 荻原裕幸 |
| 歌集 | 『リリカル・アンドロイド』 |
 tankalife
tankalife楽しい歌で、読むと心が軽くなります。ポケットを空にしても、ポケットからまだ何か音が聞こえてくるのです。童謡「ふしぎなポケット」のビスケットが何となく思い出されますが、この歌のポケットには、どんどん増えていくビスケットのようなものが入っているのかもしれません。ポケットを空にしたことと二月であることは直接的には関係がないように思いますが、「もう二月なのに」がアクセントになって読むたびに癖になります。音が鳴ることで何かが入っている方へ導かれますが、具体的に何が入っているか詠われていないからこそ、二月のポケットの中身に、無限の想像が膨らむのではないでしょうか。
生きていることが迷惑となる二月 日陰に解けぬ雪の強情
| 作者 | 俵万智 |
| 歌集 | 『チョコレート革命』 |



人に迷惑をかけずに生きていくことは、そもそも難しいことかもしれません。「生きていることが迷惑となる」は、迷惑をかけたくがないと思うがゆえに生まれた思いでしょう。自分の存在価値が改めて問われます。しかし、迷惑になると感じているからといって、死を選ぶわけではありません。これからも生きていかなければなりません。二月の日陰に解けない雪の粘り強さが、たとえ迷惑であっても、迷惑をかけながら生きていくしかないという姿と重なります。ただ、迷惑をかけていることを否定的に捉えるのではなく、迷惑をかけて生きていることをある程度は肯定しているのではないでしょうか。迷惑であることを全否定してしまうと、そもそも生きていくことはできないでしょう。究極のところ、迷惑をかけたとしても、生きていることが一番大切なことなのだと改めて感じさせてくれるのではないでしょうか。
行き場なきマスクの内の悶々が二月の空をうすく覆へり
| 作者 | 春日いづみ |
| 歌集 | 『地球見』 |



新型コロナウイルスの流行で、多くの人がマスクを着用するようになりました。マスクで隠れた顔からは、本当の表情を読みとることが難しくなりましたが、それぞれの人がマスクの内に悶々としたものを抱えているのでしょう。寒い二月の空を覆っているのは、雲ばかりではないようです。一人ひとりの悶々は小さくても、マスクを着用している人すべての悶々が集合すれば、空に浮かぶ雲よりも広範囲に薄い膜をつくってしまうのです。何ともやり場のない気持ちが滲み出ている一首だと感じます。
フリスビーが風をつかんでゆっくりと胸にふくらむ二月の夕陽
| 作者 | 岡野大嗣 |
| 歌集 | 『サイレンと犀』 |



もしも”風に乗るフリスビー”という表現であれば、容易に思い浮かぶ表現ですが、フリスビーが風をつかむという捉え方には独自性が感じられます。フリスビーが意思をもって空中を飛んでいる情景が想像されます。二月の夕陽は、寒い空気にすっきりと浮かび上がるように思いますが、フリスビーの背後にこの夕陽が現れたのかもしれません。フリスビーの円さ、夕日の円さが重なり合わり、その両方が胸の内部にだんだんと膨らんでいくような印象を受け、壮大な自然と一体化していくような人間の姿を感じる一首です。
自販機に缶コーヒーの落ちる音 二月の夜の底に響いて
| 作者 | 犬養楓 |
| 歌集 | 『救命』 |



医師として勤務している作者ですが、この歌を読む際は、その情報を背景に想像しながら読む方がより一層「缶コーヒーの落ちる」ときの静寂さが増すのではないかと感じます。救急対応の合間、一息つけるわずかな時間が訪れた場面でしょうか。自販機で缶コーヒーを買いますが、缶コーヒーが落ちる音が思いのほか響いたのでしょう。落ちる音が聞こえるまでは意識していなかった二月の夜の静寂が、落ちる音が聞こえたことを起点として、突然に意識されたのではないでしょうか。それほど、この場所のこの夜のこの時間は、静かだったのでしょう。状況的にも静かであると同時に、救命に当たる作者にとっての心情的にも静かだったのではないでしょうか。
忘れるな二月ぼくらも鳥となりこの惑星をささえあうこと
| 作者 | 正岡豊 |
| 歌集 | 『四月の魚』 |



不思議な一首です。二月になれば鳥になるというところも興味深いですし、鳥になって惑星を支えるというところも、なぜそうなのか疑問を感じながらも妙に惹かれます。「ぼくら」は人間のままでは、惑星を支えることはできないのでしょうか。鳥だからこそ、惑星を支えることができるのでしょうか。しかも「ぼくら」は協力して惑星を支え合うというのです。「ぼくらも」の「も」に、鳥の世界へ仲間入りする様子が想像できるでしょう。「忘れるな」の初句が力強く、惑星を支え合うことがまるで当然であるかのように、説得力をもって迫ってくる一首です。
ライナスの毛布になって包む夜のしんしん積もる二月のひかり
| 作者 | 高田ほのか |
| 歌集 | 『ライナスの毛布』 |
| 補足 | 「ライナスの毛布」とは、お気に入りや愛着を指す言葉で、漫画『ピーナッツ』に登場するライナス・ヴァン・ペルトがいつも肌身離さず毛布をもっていることからそう呼ばれています。一般的には安心毛布といわれる言葉です。 |



しんしん積もるのは雪ではありません。「二月のひかり」が積もっていくところに明るさと優しさを感じます。ライナスの毛布が夜をやわらかに包み込んでいるイメージがふくらんでいくのではないでしょうか。そこには焦りや不安は感じられません。毛布を抱くときのような安心感が二月の夜に満ちていく歌で、その安心感を読み手も享受できる一首ではないでしょうか。
この冬の二月の湿気を含みいる夜の落花生を食い尽くしたり
| 作者 | 永田淳 |
| 歌集 | 『1/125秒』 |



梅雨の時期のようなじめじめとした湿気ではなく、どちらかといえば乾燥しやすい二月の湿気が詠われています。この落花生は、乾燥しやすい中でも湿気を含んで、少しやわらかくなっているのでしょうか。「食い尽くしたり」は、美味しすぎて食べきってしまったとも採れますし、何か得体のしれない感情に任せて食い尽くしてやったとも採れるでしょう。後者の採り方には、落花生を食べ尽くすという行動の怖ろしさが感じられると思います。落花生の旬の時期とは外れた二月という限定が、一層一首を際立たせているように感じます。
二月尽 風が強くて「かぜつよ」とツイートするときもう止んでいる
| 作者 | 平出奔 |
| 歌集 | 『了解』 |



今のX(旧Twitter)に関わる歌です。「風が強い」と入力するのではなく、省略して「かぜつよ」。「かぜつよ」はくだけた表現に思えますが、その分親しみ度合いは増しているでしょう。一瞬の突風でしょうか。この風の強さをツイートしたくなったということは、このときの風は普段の風とは違って感じられたのでしょう。実際ツイートしたのでしょうか、それとも確定ボタンを押す前に風が止んでいることに気づいてツイートしなかったのでしょうか。「するとき」が微妙な表現で、どちらとも採れる仕掛けになっています。二月の終わりの風の存在と、その風に一時的に行動を操られてしまったような主体の存在が浮き彫りになっていて、興味深い一首です。
のど飴をのどがきれいなのに舐めて二十代最後の二月を終える
| 作者 | 虫武一俊 |
| 歌集 | 『羽虫群』 |



二月は毎年やってきますが、「二十代最後の二月」はたった一度きりであり、二回訪れることはありません。この歌からは、どこかやりきれなさのようなものが感じられます。のど飴は大抵喉が痛いときや違和感があるときに舐めることが多いと思いますが、ここでは喉がきれいな状態であるのに舐めているのです。もちろん喉が痛くなくても舐めたければ舐めてもいいのですが、こう詠われると、のど飴を舐めている行為が違和感をもって伝わってきます。それを主体も認識しているのでしょう。本当はこうじゃないし、何か違うんだけど、今ある現状を仕方なく受け入れている姿が浮き上がってこないでしょうか。二句三句の句跨り「きれいな/のに」も、違和感を増長しているでしょう。寒い二月を終え、これからはあたたかい春に向かって、違和感のない日々を送れるのかどうか。それは読み手の想像に委ねられているのかもしれません。
北側に苔生えているような鼻さすりつつ行く二月のチャペル
| 作者 | 中沢直人 |
| 歌集 | 『極圏の光』 |



緑豊かな場所に建てられた、結婚式場としてのチャペル。友人の結婚でしょうか、自分自身の結婚でしょうか。「北側に苔生えているような」は意味から考えれば「チャペル」にかかるのが自然なように思います。しかし、語の配置から考えると「鼻」にかかるように読んでしまいます。むしろ「鼻」にかかった方が面白いのではないかという気がしてくるではありませんか。鼻は北側を向いているのでしょう。苔が生えているような鼻とは、肌が荒れた鼻、あるいは腫れ物ができた鼻のようなイメージでしょうか。すべすべの鼻という感じではありません。そんな鼻を気にしながら二月のチャペルにいる主体の姿が、愛おしく感じられる一首です。
喪の服をクリーニングに出さぬままみぞれまじりの二月が終わる
| 作者 | 藤島秀憲 |
| 歌集 | 『すずめ』 |



喪服はスーツと違い、毎日使用するものではありません。弔事において今回使用した喪服を次に使うのはいつになるかわかりません。ですから一度使った後はクリーニングに出すことが多いでしょう。ここではクリーニングに出していないわけですが、クリーニングに出さないというわけではなく、出そうとは思いながらも延び延びになっている状況だと思います。すぐに出せない理由は何でしょう。ただ面倒だからというわけではなさそうです。弔事の余韻を引きずっているのか、クリーニングに出すことで亡くなった人との関係がリセットされてしまうからなのか。とにかく喪服を使用したときの状態を、現状維持していたい思いが感じられます。「みぞれまじりの二月」が一層その思いを募らせますが、二月の終わりが新たな一歩へ踏み出す境目となるのかどうか、そんなことを考えさせられる一首です。
尖るのはあなたでなくてはいけないが樹皮ひりひりと二月が尖る
| 作者 | 大森静佳 |
| 歌集 | 『ヘクタール』 |



誰が尖って誰が尖らないのか、何が尖って何が尖らないのか。「尖る」ことを突きつめた歌です。尖っているのは「二月」です。二月が尖るとは、寒さに研ぎ澄まされた二月のイメージでしょうか。「樹皮ひりひりと」とあるので、極寒に立つ樹木の尖ったようなイメージも重なります。余分なものがそぎ落とされ、寒さと共に二月だけが尖っていく状況が思い浮かんできますが、二月が尖ってほしいわけではないのです。本当は「あなた」が尖ってほしいのです。そして「あなた」が尖るべきだという思いが強く刺さってきます。鈍さではなく、鋭さへの希求が、二月の寒さの中に顕ち上がってくるような一首ではないでしょうか。
種子のくるしみはめざめるジュラルミンのつばさを濡らす二月の雨に
| 作者 | 魚村晋太郎 |
| 歌集 | 『バックヤード』 |



「ジュラルミンのつばさ」は飛行機の両翼のことでしょう。二月の雨に飛行機の翼が濡れています。この歌が収録されている一連には、鳥インフルエンザを詠った歌があり、「種子のくるしみ」は鳥インフルエンザの蔓延と殺処分に通じるものではないでしょうか。その背景を置けば、「つばさ」は鳥の翼に重なり、雨に濡れる「つばさ」に、どうすることもできないやるせなさが滲み出てくるように感じます。この「つばさ」はもう羽ばたくことはないのでしょうか。それとも再び自由に飛ぶことができるのでしょうか。二月の雨に濡れたジュラルミンの冷たさが残り続ける一首です。
奇跡 でなければ薄塩ポップコーン 二月の朝によく似合うもの
| 作者 | 服部真里子 |
| 歌集 | 『遠くの敵や硝子を』 |



二月の朝に似合うものとして「奇跡」と「薄塩ポップコーン」が提示されている発想にまず驚きますが、さらに驚くのは「奇跡」からはほど遠い「薄塩ポップコーン」に移る展開そのものです。「奇跡」は自力だけではどうにもならず、他力のあらゆるサポートが必要な気がしますが、「薄塩ポップコーン」は自力だけで何とか手に入りそうです。「でなければ」の変わり身の早さや、その落差が何とも心地よく感じます。しかし、一旦「奇跡」を初句で見せられてしまうと、「薄塩ポップコーン」はただのポップコーンではなく、奇跡のイメージを残した上でのポップコーンとなり、その位置づけが「奇跡」側にやや引っ張られてしまうように思います。そのとき「薄塩ポップコーン」は二月の朝に似合う特別なものとして存在感を放ち始めるのです。
ほふほふと饂飩をすする音だけが二月の晩にこだまして
| 作者 | 知花くらら |
| 歌集 | 『はじまりは、恋』 |



うどんを啜る場面ですが、ありきたりな”つるつる”ではないのですね。「ほふほふ」というオノマトペがとても効果的に感じます。寒い二月の晩に食べるうどんはやはり温かいうどんでしょう。鍋焼きうどんかもしれません。熱々のうどんを啜る様が「ほふほふ」に充分に表れているのではないでしょうか。周りは静かさに満ちていて、啜る音だけが響く状況は、うどんに向き合う主体の姿と、うどんと、うどんの音だけをひっくるめて徐々にフォーカスしていくような印象がある一首です。
思いだす庭の二月に色彩はなくて眠っている父さえも
| 作者 | 田中ましろ |
| 歌集 | 『かたすみさがし』 |



記憶の中にある庭の二月は、色彩のないまま保存されているようです。実際に見た庭にはもちろん色彩はあったのでしょうが、思い出すときに浮かび上がる庭に色彩はありません。それはなぜなのでしょう。この歌を含む一連から、父が病んでいることがわかりますが、そのことも影響しているのではないでしょうか。「眠っている父」でさえも色彩がない様子は、どちらかといえば活力のなさというか、静的というか、停止状態というか、そのようなイメージがもたらされます。記憶の中の庭と父にどんなに色彩をつけようとしても、このときの庭と父には色彩をつけることはできないのでしょう。色彩のない記憶は色彩がないがゆえに、特別な記憶となってよみがえってくるのではないでしょうか。
水に顔を洗へるわれの頭上にて二月の虻の羽音うつろふ
| 作者 | 横山未来子 |
| 歌集 | 『花の線画』 |



描写の美しい歌です。まず視点が水、顔、頭上と徐々に上方へ移動していく様が丁寧に詠われています。そして頭上に何が現れるかといえば「二月の虻」。顔を洗っている自分は虻の姿を見たわけではなく、虻が飛ぶ音だけを感じているのです。上句は触覚中心で、下句は聴覚中心に展開していきます。この歌は視覚が前面に出ていませんが、虻が移動する様子がありありと浮かんでくるのではないでしょうか。二月の水の冷たさを感じることによって感覚が一層研ぎ澄まされ、虻の羽音とその軌道がより鮮明に感じられたのではないでしょうか。
一年は円卓にしてどの席も主賓席なり二月に座る
| 作者 | 石川美南 |
| 歌集 | 『架空線』 |



一年十二ヶ月に優劣をつけることはできませんが、十二月が終わればまた一月が始まるわけであり、それは直線的というよりも円環的と捉えた方がいいのでしょう。「一年は円卓にして」というのは、この円環的な状況をわかりやすくイメージさせてくれる表現です。そして優劣をつけられないことは「どの席も主賓席」に端的に表されています。ここに今十二ヶ月と同じ数だけの椅子、つまり円卓十二個の椅子があるとして、仮に座るとすればどこに座ることを選択するでしょうか。円卓の椅子の配置を時計の文字盤に見立てると、わかりやすいでしょうか。今回主体は二月を選びました。また別の機会に同じように二月を選ぶとは限りません。一月から十二月のイメージを浮かべたとき、二月というのはどちらかというと目立たない月かもしれません。一月のような始まりの月でもなく、三月の卒業、四月の入学のようなこともなく、七月八月のような夏真っ盛りというわけでもなく、十二月のような締めの月というわけでもなく…。どの席も主賓席とはいいながら、二月を選択したところに、主体の思いやりのようなものを感じる一首ではないでしょうか。
吾を待つ窓にも雪か町中に空室情報溢れる二月
| 作者 | 小川佳世子 |
| 歌集 | 『水が見ていた』 |



歌集において、この歌に続く一首は〈空き部屋に案内されて見る窓の月と二人で棲みてみたしも〉。「吾を待つ窓」とは空室の窓のことでしょう。「吾を待つ」とは、まだ案内されていない状態でまだ見ぬ窓を想像しているのか、それとももうすでに空室の窓は目の前にあるのだけれど、この部屋に住むことになれば将来的にこの窓が私を迎え入れてくれるという意味なのか、どちらとも捉えられるように思います。明らかなのは空室情報が溢れているということです。雪の舞う二月の町の空室の多さは、どこか物悲しさを湛えているように感じます。しかし、雪を映せる私のための窓がそこにあること、それだけでとても素晴らしいことなのではないでしょうか。
晴れ男と道で別れて歩き出せば二月の中之島の粉雪
| 作者 | 谷村はるか |
| 歌集 | 『ドームの骨の隙間の空に』 |



中之島は大阪市北区にある地名です。晴れ男と一緒に歩いていたうちは、雨も雪も降っていませんでした。しかし、その晴れ男と別れた後、中之島を歩いていたところ、粉雪が降ってきたのです。状況としては、二月の中之島に粉雪が降ってきただけということになりますが、大阪で雪が降ることはめずらしい方の部類に入るでしょう。そのめずらしさを、晴れ男と道で別れた後ということに紐づけることで、粉雪が降ったことをより一層特別なこととして捉えなおそうとしているのではないでしょうか。晴れ男と粉雪との因果関係は定かではありませんが、このときの主体にとっては、この因果関係を抜きに粉雪を見上げることはできなかったのかもしれません。何も晴れ男と道で別れたからだといいたいわけではないでしょう。しかし、中之島の粉雪に対して、晴れ男と道で別れた後であったという状況だけは認識しておきたいといった感情でしょうか。殊更声高に因果関係を示したいわけではないでしょうが、そのときの状況が淡々と提示されることで、このときの粉雪はこのときだけの粉雪として思い出されることになるのだと感じます。
かのときの二月岬の潮風になびきてありしえり巻きのQ
| 作者 | 杉﨑恒夫 |
| 歌集 | 『パン屋のパンセ』 |



見立ての歌です。二月の岬に立っていたときのことを振り返っているのでしょう。そのとき、岬の潮風が結構吹いていたのでしょう。えり巻きが風に靡いていたのですが、結句の「えり巻きのQ」がこの一首のポイントだと思います。「Q」というアルファベットたった一文字で、えり巻きの巻かれている形状を、読み手に伝えてくれているところが秀逸だと感じます。えり巻きをしていたのは自分でしょうか、それとも同行した誰かでしょうか。誰が巻いていたかよりも、「えり巻きのQ」の映像だけが、かのときの記憶として鮮明によみがえってくるような一首です。
逆上を後悔が追いぬくように二月の雨がふいに温しも
| 作者 | 島田幸典 |
| 歌集 | 『駅程』 |



よほど変わった状況でない限り、「逆上」も「後悔」も、自ら望んで得ようとするものではありません。本当は逆上するつもりはなかったけれど、仕方なく逆上してしまったとか、後悔なんてしたくないと思っていたけど、振り返ってみれば後悔が込み上げてくるといったことなのだと思います。さて、逆上と後悔を比較したとき、どちらがよくてどちらが悪いといったものではありませんが、この歌では逆上と後悔が対比的に詠われています。ついカッとなり逆上してしまったとして、時間が経過すればするほど、そのときの怒りや負の感情は静まっていきます。一方、一時の感情が静まっていくほどに湧き上がってくるのが後悔です。逆上したことを後悔し出すという状況でしょう。「逆上を後悔が追いぬく」というのは、まさにそのような状況であり、後悔の気持ちの方が強くなっている状態でしょう。そして、下句では「二月の雨」が登場しますが、自分が雨に濡れている場面を想像します。最初は皮膚に冷たく感じていた二月の雨ですが、長時間雨に濡れ続けていると、だんだんと雨が温かく感じれられてきたのでしょう。このような経験のある人も多いのではないでしょうか。冷たいから温い状態へ移る喩えとして「逆上を後悔が追いぬく」という推移をもち出しているところが、とても納得でき巧みな一首です。
ボートみな裏がえされてみずいろの腹を見せおり二月あたたか
| 作者 | 中津昌子 |
| 歌集 | 『風を残せり』 |



川でしょうか、湖でしょうか、あるいは海でしょうか。おそらく手漕ぎボードだとは思いますが、そのボートすべてが裏返されている場面を捉えています。寒い二月においても、太陽が出ていて暖かさを感じる一日のことでしょう。通常ボートを見るときは水に浮いている状態であり、ボートの裏側をまじまじと見る機会はそうありません。しかし、この日はすべてが裏返され、「みずいろ」を晒していたのです。底を「腹」というのかどうか知りませんが、「みずいろの腹」といい切ったところにボートの存在感と色の鮮明さが立ち上がってくるように感じます。普段とは異なるボートという具体的な光景があることによって、二月の暖かさも具体的に伝わってくる、そんな一首だと感じます。
宵闇に追はれ追はれて夕映えは二月の空を沈んでいつた
| 作者 | 山木礼子 |
| 歌集 | 『太陽の横』 |



何かが存在するためには、別の何かは同時に存在できないといったケースもこの世にはあるでしょう。この歌に登場する「宵闇」と「夕映え」はまさにそれで、共存できません。夕映えの時間帯に宵闇は姿を現すことはなく、宵闇の時間帯に夕映えは存在できません。ここでは夕映えが主となっていますが、夕映えが宵闇に追われている様が伝わってきます。宵闇からすると、夕映えは早くどこかにいってくれないかな、という感じでしょう。そうでないと自分の出番がないからです。宵闇に追われた夕映えは居場所をなくし、もうこれ以上この場に居続けることはできず、やむにやまれず「二月の空」から姿を消してしまったのです。その後は宵闇が空に広がりますが、その宵闇もいずれ朝にとって代わられるのです。日は繰り返されるとはいえ、追われた夕映えが沈んでいった瞬間というのは、夕映えの立場で見ると、やはり寂しさを伴わずにはいられないのではないでしょうか。
あえかなる涅槃団子を拾ひにき二月の虹のごとき記憶よ
| 作者 | 小島熱子 |
| 歌集 | 『りんご1/2個』 |



「涅槃団子」とはお釈迦様の命日である旧暦2月15日に行われる法要「涅槃会」で参拝者に配られる団子のことです。「あえかなる」は弱々しい、儚い意味合いですが、そのような涅槃団子を拾った過去を思い出しているところなのでしょう。「二月の虹のごとき」とは、あっという間に消える虹のイメージであり、非常に儚いことの喩えでしょうか。「あえかなる」に畳みかけるように「二月の虹のごとき」が展開され、ただでさえ儚いものに対して、それを思い出すという行為それ自体も儚いという、二重の儚さが感じられる一首だと思います。
家にゐて外にゐてこころ落ち着かず酢のやうに寒い二月のまひる
| 作者 | 小島ゆかり |
| 歌集 | 『エトピリカ』 |



悩み事があるのでしょうか。深刻な悩みというのではなく、些細なものかもしれませんが、どうも心が落ち着かないようです。家にいても外にいても落ち着かないのは、あるいは悩みというよりも不安に近いものがあるのかもしれません。とにかく心が落ち着かないわけですが、季節は二月で真昼です。「酢のやうに寒い」が魅力的な表現です。酢と寒さの関係を論理的にいうのは難しいのですが、さまざまある調味料の中で酢の酸っぱさが選ばれており、「酢のやうに寒い」は酢を味わうときの酸っぱさのように引き締まった感じの寒さを表しているようなイメージと捉えました。醤油でも塩でもソースでもなく「酢」であるところに、酢だけがもつ特徴を感じながら二月の寒さを想像するとともに、心が落ち着かない様子と酢も同時に重ね合わせながら、「酢のやうに」という喩えを存分に味わいたい一首です。
雲も雪も区別はなくて地平線わからなくなる二月はこわい
| 作者 | 塚田千束 |
| 歌集 | 『アスパラと潮騒』 |



雲も雪もその元の成分をたどっていけば、水にいきつきます。結果として顕れた雲と雪はかたちや大きさに違いはありますが、何からできているかという点で区別はありません。さて、歌の場面として見えているのは、雪が積もっている情景でしょうか。そして空は雲で覆われているのでしょう。遠くの地平線あたりを眺めると、地上に積もった雪と空を占める雲との境があるはずですが、雪と雲の白さが入り交じり地平線がわからなくなっている状況です。二月のある日のことですが、そんな情景を見て「こわい」という感情が出てきてしまったのです。区別があるということは、各々の存在をはっきり認識できるということであり、ある意味我々を安心させてくれることなのかもしれません。しかし、見えると思っていた地平線が見えないとき、地と空との境界はなくなり、その境界の消失は、自分自身の立っている場所の確実性すら奪ってしまうほどの怖さをもたらしてくるのではないでしょうか。
如月の短歌
2月は2月でも、「如月」という表現に関わる短歌を取り上げています。
きさらぎのひかりに湯気が立ちのぼるわしが飲まへんコーヒーたちの
| 作者 | 吉岡太朗 |
| 歌集 | 『世界樹の素描』 |



このコーヒーは、いや「コーヒーたち」なので複数のコーヒーカップがそこにはあるのでしょう。そして、それらのひとつとして自分が飲むコーヒーではないのです。つまりはそれらのコーヒーは他者のために用意されたコーヒーであり、主体はなぜかそれらコーヒーを見ている場所にいるのです。「わしが飲まへん」の関西弁も特徴的です。湯気が立ちのぼる様が描かれているので、まだ冷めてはいないのでしょう。一般的にコーヒーは誰かが飲むために入れられるのであり、お飾りとして用意されることはほとんどないと思います。この後誰かがコーヒーを飲むのでしょうか、それともこれらのコーヒーは誰にも飲まれることはないのでしょうか。少なくとも飲むのは「わし」ではありません。今この状況においては、コーヒーを飲むという行為がなされないことによって、「きさらぎのひかり」に立ちのぼる湯気だけが取り残されたような、どこかしら不全感のようなものが漂う一首なのではないかと感じます。
氷のいろに晴れわたりたるきさらぎのわたくし空に撓るのこぎり
| 作者 | 渡辺松男 |
| 歌集 | 『雨る』 |



「氷のいろ」とは透明に近い青色のようなイメージでしょうか。空が晴れわたっているところから、単に透明や白色ではなく、青を帯びた色を想像します。水色という言葉があるように、氷色という言葉もあるようです。さて、そのように晴れた如月の空に映っているものが何かというと、「撓るのこぎり」です。しかもそののこぎりは「わたくし」なのです。なぜ唐突にのこぎりなのでしょうか。氷から連想するに、夏祭りなどで巨大な氷をのこぎりで挽くイメージが浮かんできます。「わたくし」自身がそののこぎりになってしまったのです。かなりの想像力を働かせなければなりませんが、むしろのこぎりそのものになってしまった方がわかりやすいのかもしれません。のこぎりになってしまうほど「わたくし」は氷色に晴れる空を全身で感じているのでしょう。のこぎりになって空に撓ることこそが、このときの空には最もふさわしい状況なのだと感じます。
雨上がり如月の夜はこの傘がタクトになるほど星の合唱
| 作者 | 笹本碧 |
| 歌集 | 『ここはたしかに 完全版』 |



如月の夜、雨が降っていましたが、雨が上がってしばらくしての場面です。広げていた傘を閉じると、傘は棒状の一本に戻ります。雨上がりの夜空には、無数の星が輝いていたのでしょう。無数に輝く星の視覚的な要素が「星の合唱」という聴覚的な要素として展開されています。そのとき、自分がもっていた一本の傘は、もうタクトとみなして何ら問題はありません。いや、傘として手にもっているのはもったいない。夜空の星々に向けて、この傘というタクトをかざしてみないわけにはいきません。その瞬間、主体と夜空の星々は一体になれたのではないでしょうか。一本の傘をもっていたことは、主体にとっても夜空にとっても、とても幸運なことだったのだと思います。
歌もまたサンクチュアリとしてあるに如月の死を逃げまどふ蜘蛛
| 作者 | 黒瀬珂瀾 |
| 歌集 | 『空庭』 |



季節は如月、この蜘蛛は死ぬ運命にあるのでしょうか。死の予感から必死に逃れようとする蜘蛛の動きは、整然としたものではなく、乱れを伴った軌跡として伝わってきます。さて「歌」とはずばり短歌のことでしょう。短歌もまたサンクチュアリ、つまり外敵から守られて安全な聖域にあると詠われています。その聖域は、蜘蛛の巣が完璧に張り巡らせた領域に重ねて想像することができるのでしょう。完璧な蜘蛛の巣はバリアとなり、中央に鎮座する蜘蛛は、外敵から身を守るのに最もふさわしい場所にいることになります。しかし、完璧に見えた蜘蛛の巣というバリアも、より強大な力によって破られてしまうことがあるでしょう。そのとき蜘蛛は死を覚悟し、ただただ逃げまどうしかないのです。果たして、短歌はどうなのか。いつまでもサンクチュアリに安住できるのか。そんなことが問われているような一首ではないかと思います。
如月の闇は本当に甘いから舌をまっすぐ伸ばしてごらん
| 作者 | 松平盟子 |
| 歌集 | 『うさはらし』 |



「闇」「甘い」「舌」「伸ばしてごらん」と続くと何やら官能的な香りの漂う一首です。闇に甘さがあるというのはあまり聞いたことがありませんが、「如月の闇は本当に甘い」といわれると、ただただうなずくしかありません。その甘さを味わうためには舌をまっすぐ伸ばせばいいのです。闇の中恐る恐る舌を伸ばすと、そこには今まで味わったことがないような甘さが広がっているのでしょう。怖いのは最初だけで、一旦如月の闇の甘さを知ってしまうと、もうその虜になってしまうしか残された道はないように感じます。
花に遣る水の具合をはかりかね優しさを問ふ如月の朝
| 作者 | 小川真理子 |
| 歌集 | 『母音梯形』 |



如月の朝に、花に水遣りをしようとしている場面でしょうか。この日は雨が降っていないのでしょう。花に水を遣ろうとするのですが、どれだけの水を遣ればいいか迷っているようです。水が少なすぎても花を枯らしてしまうでしょうし、反対に多すぎてもやはり花を駄目にしてしまうでしょう。優しさを問うているのは花に対してでしょうか、それとも誰か他者に対してでしょうか。あるいはその両方でしょうか。優しさを問うた結果、果たして水の具合は定まったのでしょうか。いや、この日の朝に水遣りの具合はもう定まらないのかもしれません。であれば、水遣りはあきらめて、ひたすらに優しさを問い続ける、そんな朝が一日くらいあってもいいのではないかと、そんな風に感じてしまいます。
新しき妄想の種蒔かれたる大地を濡らすきさらぎの雨
| 作者 | 大田美和 |
| 歌集 | 『きらい』 |



種が大地に蒔かれるとき、その種は植物や食物の種であることがほとんどでしょう。太陽の光と恵みの雨により、その種はやがて発芽し、我々に実りをもたらしてくれます。しかし、この歌で蒔かれているのは、そのような目に見える実りのための種ではなく、「新しき妄想」の種なのです。そもそも「新しき妄想」とは何なのでしょう。誰にとっての妄想なのでしょう。それを想像することはもはや読み手に委ねられているのでしょうか。「きさらぎの雨」という恵みを一切に浴びた種は、やがて成長していくのでしょうが、そのとき現れるものは何でしょう。妄想でしょうか、それとも妄想を超えた何かでしょうか。成長した種はもう誰にも手をつけられないようなものに変化するのでしょうか。まだ種であるうちが幸いなのかもしれません。妄想ほどやっかいなものはない、そんな印象のある一首です。
きさらぎの湖慄へたり 漣の白とはみづに降るさくらばな
| 作者 | 川野芽生 |
| 歌集 | 『Lilith』 |



如月の湖を前にした歌ですが、ある種の定義の一首です。「漣の白」とは何か、辞書を引いても出てきません。「漣」も「白」も辞書には載っていますが、「漣の白」は載っていないでしょう。「漣の白」が何かを伝えるとき、「みづに降るさくらばな」はとても詩的でありながら納得感をもって迫ってきます。それは「白」と「さくらばな」に共通する色彩、「漣」と「さくらばな」に共通する凝縮性のようなものによるのかもしれません。二句の「慄へたり」の表記が「震へたり」ではないところに、危うさが増して感じられます。通常の二月では桜の季節と合いませんが、旧暦の如月であるところに重ね合わせが働くのでしょう。慄える湖は、降りやまないさくらばなを受け入れ続け、湖は永遠に揺れ続けていくのではないでしょうか。
きさらぎの光のマーマレード添ふ 朝の食事は祈りにあれば
| 作者 | 香川ヒサ |
| 歌集 | 『The quiet light on my journey』 |



如月の朝の食卓の風景です。明るさを感じる一首ですが、「光」「マーマレード」「祈り」という言葉が重ね合わされることによって、この明るさはもたらされるのでしょう。マーマレードのオレンジ色に朝の光が透過しており、マーマレードの暖色は光の色のイメージとも調和しているように感じます。昼や夜の食事に比べ、「朝の食事は祈り」なのかもしれません。この歌を読むと、朝一番の光あふれる食卓は祈りにふさわしいように感じます。夏の暑さを伴う光ではなく、如月の冷たい光であることが、一層そのように感じさせてくれます。マーマレードという具体性が活きた一首ではないでしょうか。
根をはやす思ひの淵にきさらぎのひかりをまとふ爪が十ある
| 作者 | 河野美砂子 |
| 歌集 | 『ゼクエンツ』 |



ピアニストでもある作者ですが、自分の指そして爪を見つめている場面でしょう。ピアノを弾くための十本の指先に、「きさらぎのひかり」が集約され、十の爪が輝いていて見えます。「根をはやす思ひの淵」とは、固く決心した心の奥深い状況を想像すればいいでしょうか。自分自身の本当の気持ちを思う中で見る十の爪は、それが存在するだけで肯定感をもって見つめることができたのではないでしょうか。冬の光に輝く爪が美しくイメージされる一首です。
きさらぎの汽水が浸す橋ありてその橋脚を攻めやまぬ潮
| 作者 | 大辻隆弘 |
| 歌集 | 『汀暮抄』 |
| ※ | 名字の「辻」の字は、正しくは1点しんにょうです。 |



汽水域に橋が架かっていますが、「汽水が浸す橋」という表現が魅力的です。この表現によって、汽水も橋も両方の存在が際立ってきます。如月の寒さに張り詰めた汽水の様子が伝わってきます。この汽水には流れがあるのでしょう。「攻めやまぬ潮」から、潮が橋脚に何度も何度も当たっている様子が浮かびます。上句は静的ですが、下句に移るに従い動的な景に変わります。言葉の頭文字の音を見ると、「きさらぎ」「汽水」「橋脚」のK音、「浸す」「橋」のH音、「その」「攻めやまぬ」「潮」のS音が効果的に配置され、読んでいてリズム感を感じる歌だと思います。
ここが故郷であるかのように如月の樹々の高さを風が響りたり
| 作者 | 三枝昻之 |
| 歌集 | 『遅速あり』 |



「ここが故郷であるかのように」とあることから、ここが故郷ではないことがわかります。主体にとって故郷でもないのでしょうし、風にとっても故郷ではないのでしょう。しかし、如月の風はまるで故郷であるかのように吹いているのです。風の響きを聞いていると、自ずと故郷が思い出されてしまったのでしょう。今ここに吹く風が記憶と結びついて、ありふれた如月の風ではなく、もうすでに思い入れのある風として感じられたのではないでしょうか。音韻の面では「ここ」「故郷」「如月」「樹々」「風」のK音が多数配置され、樹々と風のやや硬質な印象がもたらされます。